南設楽郡鳳来町立山吉田小学校
|
ふれあい食事会
―地域の一人暮らしのお年寄りを招いて―
|
 |
| 学校名 |
南設楽郡鳳来町立山吉田小学校 |
| 児童数 |
67名(男子33,女子34) |
| 実施学年 |
4,5年女子の希望者 |
| 実施児童数 |
10名 |
| 活動場所 |
本校のホール等 |
|
 |
学校5日制に伴う関連事業として、平成14年度からPTAと地域の各種団体代表からなる「未来(あす)の子館運営委員会」が組織され、年間10回程度の『未来の子館活動』を土曜・日曜日に開催している。ねらいは次のようなものである。
・自ら選択して活動に参加する態度を養う。
・土曜日、日曜日における体験の場、学びの場とする。
・山吉田ならではの活動を企画し、ふるさとを愛する心を育てる。
・地域住民と保護者が企画し、地域で子どもを見守り育てる機会とする。
11月のいきいきあいちっ子キャンペーン期間中は、地区の民生委員主催の「ふれあい食事会」に希望する児童が参加し、お手伝いすることを通して、身近な人々に支えられている地域の福祉の実情を知るとともに、活動を通してお年寄りの理解を深め敬愛の精神を養う機会になっている。
|
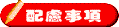 |
活動への参加に対しては、子どもたちが「自らの選択する」ことを大切にして、希望制で参加者を募っている。参加した児童が家庭や学校で体験を語ることで、学校や地域に福祉の精神が根付いていく一助になってほしいとの願いをもっている。
|
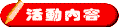 |
 (1)事前の活動 (1)事前の活動
10月26日、地区の民生委員5名とお年寄りの福祉に関する活動をしている鳳来町のボランティア団体「しゃくなげ会」3名、未来の子館運営委員2名、計10名で当日の打合せを行う。
(2)当日の参加者(計40名)お年寄り11名、児童10名、民生委員6名、しゃくなげ会4名、お話BOX(読み聞かせボランティア)4名、未来の子館運営委員2名、教員3名にて実施。お年寄りのお迎えは、それぞれの地区の民生委員の方が担当した。
(3)ふれあい食事会の流れと児童の活動
ア 調理の手伝い
しゃくなげ会がお年寄りのために考えた献立の調理を、子どもたちもエプロン姿でお手伝いをした。40人分の食器を並べたり野菜を切ったりして、「よく間に合う」とお褒めの言葉をいただくことができた。このときに炊いた4升のお米は、5年生が未来(あす)の子学習(総合的な学習)の米づくりで育てたものを使うことができた。
すごく楽しい時間 5年 三上彩佳
最初は緊張しましたが、学校の案内をしているうちに、昔の学校の話や今の学校の話をたくさんできました。私の名前や誕生日をを教えたりしました。食事では戦争の話をしたりして大人になったような気分でした。ビンゴゲームでは知らない人もいたので、教えてあげました。短い時間だったけど、お別れは悲しかったです。また、来年もぜひお手伝いしたいです。 |
イ お出迎えと校舎案内
子どもたちはお年寄りを笑顔でお迎えした後、「ここが音楽室です」など『ていねいな言葉で』を合い言葉に校舎をご案内した。また、段差のある場所では、「足下にお気をつけください」と声かけをすることができた。お年寄りが長く足をとめられたのは、明治44年からの卒業写真が掲示されている場所であった。ここで一緒にご家族をさがしたりすることで、子どもたちの緊張感もとれて、和やかな雰囲気に浸ることができた。
ウ 歌を発表
お年寄りの皆さんが知っている歌をということで「故郷」と「りんごの歌」の2曲を発表した。”うさぎおいしかの山…“の歌声に大きな拍手をいただくことができた。
エ 食事会
子どもたちがお年寄りの中に分散して一緒に食事をしたが、三世代同居の家庭の子どもが多いせいか、お年寄りとのお話にも笑顔で応対する自然な姿がみられた。
オ その他
児童の出し物の他に、お話ボックスの皆さんによる、地元に伝わる民話から取材した手づくり絵本の読み聞かせがあり、子どもたちも興味をもって聞くことができた。また、ビンゴゲームでは、お年寄りに寄り添って番号を確認するなど、ふれあいのひとときを楽しむことができた。
|
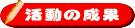 |
学校と地域の4団体が協賛する形で実施したが、互いにできる範囲で協力し合い、家庭にお年寄りをお招きするような雰囲気を出して行うことができた。子どもたちも身近な人々が活躍する地域の福祉を体験することで、地域の一員として活動する意義を学ぶよい機会になった。
|
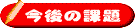 |
土曜日・日曜日はスポーツ少年団や地域の行事への参加があり、子どもの日程調整も必要である。食事会の補助が主な活動ということで参加人数にも制限がある。今年度は女子のみの参加希望者としたが、今後、男女を問わず日程の都合がつく子どもの中から自由に参加できるような工夫をしていきたい。
|