江南市立古知野中学校
|
|
 |
| 学校名 |
江南市立古知野中学校 |
| 児童数 |
812名(男子405名,女子407名) |
| 実施学年 |
全学年 |
| 実施生徒数 |
750名
62名(男28名、女34名)の生徒は、部活動の大会や高校体験入学等の行事に参加し、実施していない。 |
| 活動場所 |
校区内の神社、寺院、市役所、市民グランド、公園、公民館、資源回収集荷場、通学路や通学路周辺、小学校周辺など29カ所 |
|
 |
近年、地域で中学生の姿を見かけることが少なくなったと地域住民に指摘されるようになった。要因には、授業後、生徒は部活動や習い事等で多忙な生活を送っていることが挙げられる。また、休日も部活動や屋内での遊び等に時間を費やしていることが多いことも要因である。生徒は、地域社会と密接に関わることの希薄さや地域住民と触れ合う機会の不足が顕著である。このような状況の中で、生徒を地域の生活に根付かせることは、生徒を取り巻く大人たちの大きな課題である。
そこで、本事業は、次の3点をねらいとして、取り組むことにした。
(1) 清掃活動を通して、地域生活の舞台である場所を美しくする。
(2) 地域の方との触れ合いを通して、地域社会の一員であることを自覚する。
(3) 日ごろ、お世話になっている場所の清掃を通して、感謝の気持ちを高めるとともに、地域への愛着を深める。 |
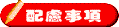 |
○自分たちの生活の舞台であり、日ごろお世話になっている場所を感謝の気持ちを込めて美しくする態度を育てる。
○清掃活動を通して、地域の方との触れ合いをもち、地域への愛着を深める。
○教職員が積極的に校外での活動に参加し、地域の方との交流を深め、地域社会に貢献する。 |
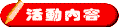 |
 11月6日(土)13:30。各家庭から清掃道具(ほうき、竹 ぼうき、ちりとり、くさみ)やリヤカーなどを持ち込んで地域清掃が始まった。 11月6日(土)13:30。各家庭から清掃道具(ほうき、竹 ぼうき、ちりとり、くさみ)やリヤカーなどを持ち込んで地域清掃が始まった。
通学班ごとに、清掃場所を決め、PTAの地区委員さんや保護者の方、地域の方とともに、清掃活動に取り組んだ。
11月の第1土曜日、秋晴れの空のもとで、取り組むようになって今年で4回目の活動は、年々、生徒の意識が高まり、自分たちの地区を美しくしたいとの気持ちを持って清掃に取り組むようになってきた。
神社や寺院では、季節柄、落ち葉が多く、落ち葉を集めることも一苦労で、参加した生徒や保護者、地域の方の額には汗が光った。リヤカーやビニル袋に一杯になるたびに、神社や寺院が掃き清められていく実感をもつことができた。
小学校周辺の清掃の生徒たちは、1〜3年前の学舎を訪れ、後輩たちのために、今、自分たちができることを精一杯行おうという気持ちがみなぎり、瞬く間にきれいになっていく様子を見ることができた。また、公園を分担した生徒たちは、幼児や児童の頃、よく遊んだ当時の思い出に浸りながら、ここを訪れる親子連れや児童らのために一生懸命、清掃活動に取り組んだ。
市役所や市民グランド、公民館などの公共施設の清掃活動に取り組んだ生徒は、あまり馴染みのない場所であったり、現在の自分たちの生活と直接結びつかない場所であったりではあるが、地域の生活に欠かすことができない場所であることを自覚し、社会の一員として貢献しようと真剣に清掃活動に取り組んだ。 |
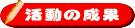 |
地域清掃の2日後、今年、初めて参加した1年生数人から次のような話を聞いた。「私は、地域での清掃活動は嫌で、しぶしぶ参加しました。始めは嫌々行っていましたが、そのうち、地域の方から、『えらいねえ。すごいね』と声をかけられました。何かとても良いことをしているんだなあと感じるようになりました。いやと思っていた気持ちが、清掃が終わる頃には、清々しい気持ちに変わっていました。自分たちが住んでいる地域の美化に、汗を流すことは、とても大事なことだと思いました。私は、地域の方たちの真剣な態度や優しさに触れることができ、とても満足しています。来年も頑張ります」。生徒たちの話に見られるように、地域清掃は、生徒に地域への貢献と地域の一員としての自覚を植え付けた貴重な体験活動であったと考える。
 地域によっては、母親だけでなく、父親の参加も見られた。保護者や地域の方とともに取り組んだ清掃活動は、生徒を地域の宝としてとらえ、地域社会全体で育てる良い機会となった。 地域によっては、母親だけでなく、父親の参加も見られた。保護者や地域の方とともに取り組んだ清掃活動は、生徒を地域の宝としてとらえ、地域社会全体で育てる良い機会となった。 |
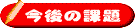 |
地域の方との交流、地域への感謝と貢献を目標に始めた地域清掃が定着してきた。今後も目標の具現化を目指した取組を継続強化していきたい。
このためには、学校行事部会、職員会議、PTA全委員会を通じて、目標の具現化を目指して、具体的な方策を協議し、改善を図っていくことが重要である。
地域によって、保護者を始めとして、地域の方の参加が若干少ないことがあった。学校後援会、地区委員会などに働きかけ、啓発活動を充実させていきたい。 |