小牧市立三ツ渕小学校
|
|
 |
| 学校名 |
小牧市立三ツ渕小学校 |
| 児童数 |
327名(男子160名,女子167名) |
| 実施学年 |
全学年 |
| 実施児童数 |
327名 |
| 活動場所 |
学校が借用している田んぼ |
|
 |
・田植えから収穫、餅つきまでの一連の活動を通して米作りの苦労や収穫の喜びを味わう。今回は稲刈り体験をキャンペーンに当てはめた。
・地域のボランティアやPTAの協力を得ながら活動を行い、お互いに触れあいの時を持つことにつなげる。 |
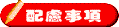 |
・服装は汚れてもよい長袖長ズボンとする。また、のこぎり鎌を扱うが、鎌を持つ反対の手には必ず軍手をはめる。
・稲に対するアレルギー児童は、見学するなどの配慮をする。
・麻ひもで稲を束ねるため、麻ひもを結ぶ練習を各学級で指導しておく。 |
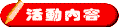 |
<稲刈りまで>
6月に4年生から6年生が手作業で餅米の田植えを行い、1年生から3年生は見学をする。田植えが終わった後、3回ほど、稲の様子観察する。その中で2年生は生活科の時間を利用してお米をスズメから守ろうとかかし作りを行う。どの学年も突然、稲刈りを迎えるのではなく、植えた稲が大きく生長し、黄金色に色づいてきて稲刈りとなる必然性を感じるように配慮している。
勤労生産的行事の係が10月はじめの職員会議で稲刈りの提案をする。
教頭はボランティアへの案内状、PTA全委員会での協力の依頼などを行う。
校務主任はのこぎり鎌80本、麻ひも2500本、刈り取る目印のカラーコーンなどを準備する。
 <稲刈り体験> <稲刈り体験>
朝、9時頃にはボランティアやPTAの方々が集まりはじめ、ボランティアの方が稲の露を竹でなでて落としてくださる。
9時半頃、まず最初に2年生が田んぼに来て、田んぼの脇でのこぎり鎌の使い方、4株から5株を束ねること、ひもをしっかり結ぶこと、安全面の注意などを受けた後、ボランティアの方にあいさつをして稲を刈り始める。ボランティアの方は「もう少し、下を切るといい」とか、「そろえて束ねるんだよ」とか、児童に教えてくださる。
2人一組で行い、一人が稲を刈って、もう一人が束ねる。交代して行うようになっている。30分ぐらいで2年生の活動が終わった後、3年生と4年生が田んぼの両端から刈り始める。その次に5年生、最後は6年生と1年生である。6年生と1年生は学校からペアを組んで歩いてくる。6年生は6回目であるためかなり慣れており、1年生に上手に教えている。
 2年生が刈った後、スペースができると脱穀が始まる。今はコンバインが主となり、脱穀機は見かけないがボランティアの一人が大事に保管をしていてくださるおかげでできる。わらは田んぼの脇に運ばれ、干される。わらもずいぶん貴重になり、2月に行う「伝承の会」で縄ない体験に使われたり地域の方に分けられたりする。 2年生が刈った後、スペースができると脱穀が始まる。今はコンバインが主となり、脱穀機は見かけないがボランティアの一人が大事に保管をしていてくださるおかげでできる。わらは田んぼの脇に運ばれ、干される。わらもずいぶん貴重になり、2月に行う「伝承の会」で縄ない体験に使われたり地域の方に分けられたりする。
<稲刈り後>
収穫される餅米は毎年300キロ余りになり、収穫感謝祭で餅つきをして全校児童で味わう。今年は創立130周年に当たり、記念式典の日にお祝いの赤飯として児童全員と来校者に配られた。また、児童が餅米を販売する活動を行った。その残りが収穫感謝祭で餅にされる。餅つきはボランティアやPTAの協力を得て6年生が餅をついてあんこときな粉のお餅にし、各学級へ配り収穫に感謝しながら味わう。 |
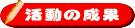 |
どろどろの田んぼにつかり、一株一株手で植えていく田植えや汗をかきながら行う稲刈り。これらは今では機械化されて見ることもできないが、敢えて手作業で子供たち全員が体験できるように組まれ、物作りの大切さや収穫に感謝する貴重な体験となっている。また、土やわらのにおいをかぎ、稲を刈ったり汗をかきながら稲の束を運ぶ体験は、お米がとれるという目に見える形で表れるためどの児童も張り切って行うことができる。
次に、活動を通して地域の方や多くのPTAとの触れあうことができ、よい関係づくりが生まれている。また、6年生と1年生のペアの稲刈り作業も、思いやりや高学年としての自覚が育まれている。
また、この一連の活動を食育の視点から見直すと、自分たちが食べるお餅という食べ物はどのように作られるのかを全員が体験して知ることができ、その素朴なおいしさの記憶はこれからの食生活を営んでいく上で貴重な体験となる。 |
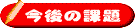 |
| 27年の伝統を誇る米作りは本校の重要な行事であり、田植え・稲刈り・収穫感謝祭と一連の作業を、延べ135名ものボランティアの協力を得ながら行っている。今後もこの活動を継続させていくよう、職員、地域、PTAがこの意義をしっかり受け継いでいくことが重要である。人が入れ替わってもこの活動の意義がうすらいでいくことのないようにしたい。 |