海部郡弥富町立弥生小学校
|
|
 |
| 学校名 |
海部郡弥富町立弥生小学校 |
| 児童数 |
609名(男子312名,女子297名) |
| 活動の名称 |
体験して食育(豆腐作り) |
| 実施単位 |
総合学習の栄養講座 |
| 実施児童数 |
26名 |
| 活動場所 |
家庭科室 |
|
 |
 体験を重視した学習活動の充実を図りながら、本校では総合学習の時間に、3年生から6年生までの児童が15の講座に分かれて取り組んでいる。中でも、栄養講座の児童は、大豆をテーマに学習を深め、秋頃には豆腐作りを行う計画を立てた。 体験を重視した学習活動の充実を図りながら、本校では総合学習の時間に、3年生から6年生までの児童が15の講座に分かれて取り組んでいる。中でも、栄養講座の児童は、大豆をテーマに学習を深め、秋頃には豆腐作りを行う計画を立てた。
この活動に取り組むことを通して、児童は地域の方々の支援を受けたり、専門家から直接教えを受けたりするなど、人との心温まる交流を深め、人への感謝の念をもつことができる。また、身近な栄養食品としての大豆を改めて見直し、自らの健康にかかわる食生活の改善にもつなげていくことができると考える。
|
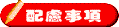 |
豆腐作りの実習に当たっては、外部講師の方や支援して下さる方々と事前に打ち合わせを行い、日程、準備物、手順、資料等を明らかにしておく。また、児童には豆腐作りの作業手順を知らせるとともに、食品衛生上守るべきことや使用する器具・用具等の安全な扱い方にふれ、指導しておく。
|
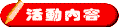 |
栄養講座の児童は、4月当初から総合学習の時間に、大豆に含まれる栄養について、講義を聴いたり自分たちで調べたりして知識を深めてきた。5月には学校の畑に大豆の苗を植え、栽培にとりかかった。7月にはしっかり実が付き、収穫が楽しみであった。その後、鳥や虫に食われたりして予想より収量は減ったものの、9月には、実った大豆を収穫することができた。
このような体験学習の後、豆腐作りの実習を行うことになった。
豆腐作りの講師は、名古屋市の豆腐製造販売店にお勤めの、柘植恵介氏に依頼した。
また、PTA活動部「ウエルネスキッチン倶楽部」のお母さん方にも手伝っていただくことにした
○ 豆腐作りの実習
<「いきいきあいちっ子キャンペーン」体験活動の一環として>
この日は、身支度を整え、みんなであいさつを交わして、実習に取りかかった。
はじめは豆乳作りである。ふやけた大豆を、同量の水とともにミキサーにかけ、それがきめ細かなクリーム状の液になったところで鍋に移して火にかける。焦がさないように液を撹拌しながら温度を上げ、沸騰する前に布袋に移し取ってよく絞る。この絞り汁が豆乳である。豆乳を絞る時には、児童は熱さにためらいながらも、交代し合い、協力し合って取り組んでいた。
次は豆腐に仕上げる作業である。できた豆乳を火にかけ、今度は75℃になるまで撹拌しながら加熱する。この時の温度管理が重要である。適温に達したところで火を止め、ニガリを素早く注ぎ、豆乳とよく混ぜ、それが鍋の中で固まるのを待つ。この一連の作業は、児童にとってはかなり難しいものであった。
しばらくすると豆乳が固まり、豆腐ができる。これを、内側に布を敷いた木枠の中に移し入れてふたを載せ、上から軽く重しをかけておく。やがて、木枠の型を抜き取ると、そこに見事、きれいな四角の豆腐が出来上がっていた。
 児童の間から、喜びの声があがったことは言うまでもない。初めて自分たちで作った豆腐の味がどんなものか楽しみであった。各自、皿に豆腐を切り分け、鰹節と醤油で味を調えて試食した。市販のものとは異なり、やや堅めではあったが、味は素晴らしく濃厚で、大豆の風味がよく出ていた。この日、みんなが、一つになって手作りで取り組んだ良さが、この味の中に含まれていたとことも忘れてはならない。 児童の間から、喜びの声があがったことは言うまでもない。初めて自分たちで作った豆腐の味がどんなものか楽しみであった。各自、皿に豆腐を切り分け、鰹節と醤油で味を調えて試食した。市販のものとは異なり、やや堅めではあったが、味は素晴らしく濃厚で、大豆の風味がよく出ていた。この日、みんなが、一つになって手作りで取り組んだ良さが、この味の中に含まれていたとことも忘れてはならない。
最後に、1つ1つ班を回って指導して下さった講師の柘植氏と手伝って下さったお母さん方に、児童からお礼の言葉が述べられて、今回の豆腐作りの実習を終えることができた。
|
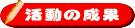 |
大豆の栄養をテーマに学習してきた講座の児童は、この体験を通して豆腐やおからを使った料理を作ることに興味を持ちはじめている。早速、「お母さんに豆腐作りの様子を話してあげたよ。」とか、「家でお母さんと作って家族で食べてみたい。」などと思い始める児童が増えてきた。このように家庭での調理を通して親子ふれあいの場が広がっていくことを、今後ともこのような体験学習の工夫を通して推進していきたいと考える。
|
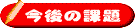 |
子どもたちの体験学習を成功させるには事前の準備が大切である。また、実際の体験中には微妙な変化のためにうまくできなかったり、時間がなくて細かな指導ができないこともある。そこで、事後に振り返る時間を十分とり、さらなる活動につながるように工夫を重ねていく必要がある。
|