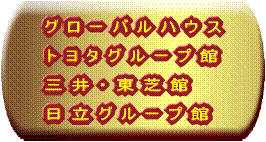4.2 各種実証実験の実施
各種の実証実験も行われました。①愛・MATE実証実験 ②ユビキタス万博実証実験 ③自律移動支援プロジェクトがくり広げられました。①愛・MATEは携帯電話の新しい姿です。携帯電話を使用するにはアンテナが必要ですが、アンテナが建てられないときには携帯電話自体をアンテナにするということです。人がたくさんいればそこがアンテナとなります。そこでお互いがデータのやりとりができます。でもその人が移動してある領域からいなくなったら、そこにいる人にアンテナを切り替えてリレーするという実験をしました。万博会場でも学生に携帯電話を持たせ実験をおこないました。 ②は観光端末として手元に持っていて、新しいパビリオンへの行き方や会場の込み具合などの情報を知ることができ、最適化してパビリオンを見ることができます。 ③杖にセンサーを入れて目が不自由な人でもパビリオンまで行くことができたり、知能車椅子の開発は、これに乗ることによってパビリオンまで誘導してくれます。トヨタはモビリティロボットを開発して、2010年までに商品化するそうです。今日のテーマ「万博が掲げた未来」が2010年には実現の運びとなります。
4.3 魅力的なパビリオン
万博のパビリオンでグローバル・ハウスというとマンモスを思い浮かべるかもしれませんが、I T ではすばらしいものが掲示されました。 ※『スーパーハイビジョン』、ハイビジョン(ラインが1,080本)は最近よくみられますが、それの4倍(4,320本)の縦横ですので、ハイビジョンより16倍情報量が増えることになります。ハイビジョンは2011年にはほぼ実現して、2025年にはスーパーハイビジョンにしようという計画がもう動いています。360度全天球型の映像システム、つなぎ目を合わせる技術も開発しました。
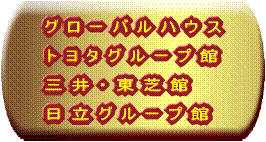
|
またロボット開発も進んでいます。なぜここ数年の間にロボットはこれだけ発展、発達したのか?コンピュータによる認知技術が高まったために ロボットの技術が進んだと考えられます。ロボットの素材が人工皮膚のようなものが出来てくると、もっと人間に近いものになってくると思われます。実際にはハードウェアより、制御技術が大きく
発達したのでしょう。例えばトヨタは人工唇でラッパを吹いたり、バイオリンのコードを押しながら弾くことができるようにもなりました。以前はピアノを弾くロボットを開発して驚いていましたが、
最近ではそれどころか弦をおさえることができるようになったのです。この発展からも将来的にはお皿を洗うロボットとかも出てきそうだと思われます。それから「バーチャルリアリティー」、
皆さん行かれたでしょうか?万博会場の日立グループの「ミックスド・リアリティ」。今現在の映像にバーチャルリアリティを合わせて、森の中に動物を浮かしたりミックスされた映像が進んでいくと
されています。さらにはフューチャーキャストシステムでは、映画の中に自分の顔が出てきたりしました。単なるバーチャルでの合成ではなく、ある部分のみ実際のものを使うといった技術が可能に
なってきました。実際にこの機能は使われつつある技術であります。