4.1 インフラとしてのインターネット
ここからはわが国の万博について述べていきたいと思います。1970年に日本で初めて万博が大阪で開かれました。このときに I T として出たのが、ワイヤレスフォン(テレビ電話)です。今の携帯電話のはしりが出たのはこの時期です。待ち合わせ案内サービス・ファックス新聞・・・このときにファックスが出来て、ファックスで新聞を送るということで、新聞社がつぶれてしまうという話になり大騒ぎになりました。コードが付いてないワイヤレス電話、現在の皇太子と故佐藤栄作総理大臣と話している写真も残っています。待ち合わせ案内サービスは、万博会場がとても広く、迷子がたくさん出たり、はぐれることが多かった。そのサービスはプッシュボタンがあって番号(例えば正面ゲートは25番)・時間・自分の番号を入れ待ち合わせの登録をしておきます。他の会場のプッシュフォンでその番号を入力すると情報が確認できるといった当時では画期的なシステムでした。また迷子になると迷子ワッペンを貼られ、情報コンピュータによって迷子センターに情報登録をして、親も他の迷子センターにて服装・年齢等の情報を入れると自分の子どもを探すことが出来ました。
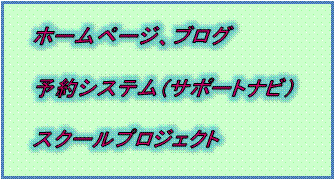 |
注:TVCML(TeleVision Common Markup Language)は、05年国際博覧会(以下、博覧会と呼ぶ)の開催を契機に、博覧会協会と在名放送事業者6社が、各放送事業者へ提供される博覧会情報の配信規則として策定された、NewsMLベースの共通情報フォーマットである。 デジタル放送地域情報XML共通化研究会(通称:TVCML研究会)ではTVCMLを災害情報の伝達に活用することをテーマに、表現の多様性や情報の一意性、速報性の向上などを図り、汎用性を持たせた規格として検討を重ねてきた。
TVCML情報は万博の博覧会協会からインターネットを通じて情報が提供されます。今までは電話にせよ、インターネットにせよ担当者が独自にその情報を元に編集して番組をだしたり、新聞を書いたりします。今回愛知万博ではTVCMLコードで統一した形で情報を提供しました。この情報コードでは自動的に編集することができるといった仕組みになっています。各局が自動でコード変換できましたので間違いがありませんでした。この経験から今愛知県ではこの技術を利用して、防災情報の提供システムへと展開していくことができます。これは日本では愛知県だけです。地震や台風があっても各局から同じ情報が出せる。万博時の経験からTVCMLが出せることが大きな展開となっています。
多くの小学校、中学校が万博を見にやってきました。この背景には【万博GOGO】というサイトができました。どういうコースを見にいくのか?また何を見たらどういうことを考えて、それに対してどういう意見を持っているか?とフォローするサイトができました。例えば小学校3年生が 「排気ガスを出さずに走る車を見ました。」 とサイトに感想の書き込みをすると、みんながネット上で意見を交換する、専門家が疑問に答えるといった子どもがただ見に来るだけの一方通行じゃない充実したものになりました。