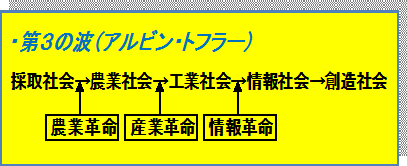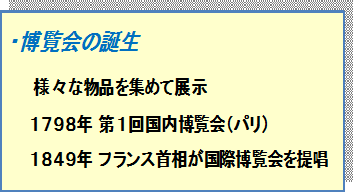さて今日は万博を、国際博覧会を通じて見る情報通信技術の発展、万博に関連して情報という切り口で万博を見ていこうと思います。内容については大きく
3つに分けて話をしておこうと思います。最初に
I T (情報)社会―時代の変化について改めて復習をしてみます。2番目には万博の歴史の中で
I T はどうやって発達してきたか?具体的に見ていきたいと思います。3つ目は2005年の『愛・地球博』を具体的に解説していきます。
1980年代のアメリカの未来学者のアルビン・トフラーが『第3の波』という本を書きました。私達人類の歴史の中に大きな波が、2回もしくは3回来ました。採集社会から農業革命へと自分達で生産すること
が出来るようになりました。その後資源を使ってモノを作って産業革命、物質社会が訪れました、ここで万博が生まれました。20世紀の後半からコンピューターという道具を発明しました。情報を加工する
ことによって、今私が講義しているのもコンピューターとプロジェクターという情報通路を使って、知識(教養)を皆さんに提供する、知ることによって学ぶことによって豊かな人生を送ることができます。
情報によって豊かさを享受する情報社会がやってきます。トフラーは「1980年代にこれからは情報の時代がくる。情報を握ったものが時代を握っていくよ」と予言しました。これをもとに詳しく見ていきます。
農業社会から工業社会に突入しました。
ヨーロッパ・イギリスから産業革命が起こって物質社会、モノ社会、色々なモノが作られる、そのものを見せましょうとする博覧会という発想が生まれます。1798年にフランスのパリで一堂に集めて見ることができる、第1回国内博覧会を行いました。≪この発想は紀元前にプトレマイオス朝が図書館を設立し、本を一箇所に集めてそこへ行けば勉強ができるという図書館の発想です。≫これと同じ発想だと思います。それを買って手に入れて商売をしよう。豊かな生活、豊かな国を
作っていこうという発想が生まれました。フランスの首相が1849年に国際博覧会をしようと話をヨーロッパのほかの国に呼びかけて、パリで開催されました。