<はじめに−ラテンアメリカ諸国のことばと言語人口−>
 |
|
田中敬一先生 |
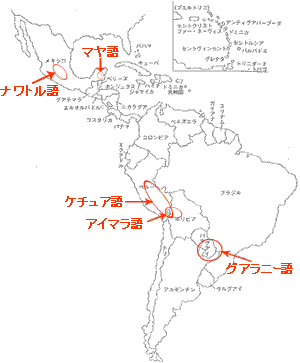 |
|
ラテンアメリカの独立国 |
左の図を見てください。今日、私が触れるのはメキシコのナワトル語とマヤ語。ペルーとボリビアのアンデス山岳地帯を中心に話されているケチュア語。チチカカ湖周辺からボリビアにかけて話されているアイマラ語。それから、パラグアイに現在も残っているグアラニー語です。このグアラニー語については、言語人口100万人を超える先住民のことばで、パラグアイの公用語にもなっており、放送局まであります。
それでは、今地図で見た国々の中で、先住民の比率の高い国と、どういった先住民の言語が話されているかを表1にまとめてみました。
まず、メキシコの人種構成を見てください。混血(メスティソ)が約80%、インディオが約10%、白人が7〜8%、その他アジア系とかヨーロッパからの移民がいます。このメキシコにおいて、言語人口の多いのがナワトル語で、約120万人の言語話者がいます。この120万人という数は1990年の統計によると、当時メキシコの総人口が8100万人。今日では1億人を越えています。インディオは1990年当時、メキシコの総人口の7.32%、すなわち530万人ぐらいが先住民インディオと言われている人たちです。その先住民インディオのうち、ナワトル語を話すのはインディオの22.7%、すなわち120万人の人がナワトル語を話しています。 それから、隣にマヤ語とありますが、実はマヤ語というのは正式な名前ではなく、ユカテク語と言います。ユカタン半島からグアテマラの方にずっと続く地帯をメソアメリカと呼んでいますが、そこでよく話されているのがマヤ語系の言語です。そのユカタン半島のメリダで中心に話されているのがマヤ語で、話者としては意外と少なく15万人程度と言われています。そしてメキシコでは、全部で54の異なる言語が確認されています。
表1「先住民比率の高い国と先住民のことば」 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
(出典:『ラテンアメリカを知る事典』から作成) |
<記述言語を持たなかった先住民の悲劇>
今度は歴史的に先住民がどのような状況に置かれて、今日に至ったかということを少しだけ触れてみたいと思います。1519年、スペイン人征服者のエルナン・コルテスが、数百名の部下を率いてメキシコの西海岸のベラクルスに上陸しました。この時スペイン軍を構成していたのは、508名の歩兵、32名の石弓の射手、大砲が16門、小銃が16、それ以外に16頭の馬、それから数えることはできませんが多数の犬、今でいう軍用犬です。当然のことながら、当時メキシコの中央高原(現在のメキシコ・シティ)に都を置いていたアステカ帝国と対立します。そして、わずか2年の後、1521年にスペイン軍は首都のメキシコ・シティに攻め上り、当時皇帝であったモクテスマ二世を殺害し、アステカ帝国を滅ぼしてしまいます。数の上では圧倒的に多数であったアステカ軍を、わずか600名の手勢を率いたスペイン軍があっという間に征服してしまうのですが、なぜそんなに征服が容易であったのでしょうか。1番目の理由として、スペイン軍がインディオの援軍を味方につけていたということです。実は当時アステカ帝国は、武力でいくつかの部族を従属させていました。このアステカ帝国に敵対する部族を、エルナン・コルテス率いるスペイン軍は味方につけたわけです。それが数千人にも及ぶと言われています。それから2番目の理由として、先ほども言いましたが、火器、すなわち銃と大砲、それと馬を持っていたということです。インディオは銃声を聞いては震え上がり、それからスペイン軍の兵士を人馬一体となった怪物と捉えたそうです。また、それ以外にも車などを用いなかったという文明上の違いも数えられるかもしれません。ところが、ブルガリア生まれの構造主義文学者、ツヴェタン・トドロフは次のように本の中で書いています。このことを私は強調したいのです。
「スペイン軍の勝利の原因はアステカ帝国が文書による記述を持たなかったことにある。実用性を欠いた絵文字
しか持たず、また口承伝承を記録の主たる媒体としたアステカ人は、スペイン軍の出現と侵攻を記録し、位置
づける術を持たなかった。」
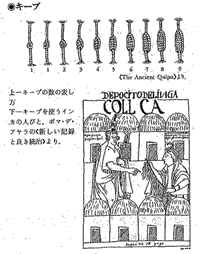 |
|
(『ラテンアメリカを知る辞典』p.128) |
<スペイン王室の統治政策と先住民インディオ>
スペイン王室はインディオを国王の臣下と見なしていましたが、決して理性を持たない人間、いわゆる野蛮人のようには見ていませんでした。つまり、スペイン人が大人ならインディオはまだ子どもだという見方です。そしてインディオを奴隷として扱わず、一家村あるいは数家村の住民単位でスペイン人入植者(エンコメンデーロ)に分け与えました。スペイン人入植者(エンコメンデーロ)は、インディオの保護とキリスト教化を手助けする引き換えに、インディオの労働力の提供を受けたわけです。ところがこのスペイン人入植者(エンコメンデーロ)たちは、その大部分が収入を得ることを目的として、インディオを虐待しました。その結果、インディオ人口が激減します。また、旧大陸から持ち込まれた疫病(はしか、天然痘、腸チフス等)により、1540年には西インド諸島のインディオは絶滅同然になります。メキシコにおいては、1519年に推定2500万人であったインディオが、約90年後には100万人強までに激減しています。これはスペイン系アメリカ全体にも言えることで、16世紀半ば、5000万人いたと言われるインディオが17世紀には僅か400万人です。18世紀末になって少し回復しましたが、それでも750万人に減りました。
<先住民文化の復権−メキシコの場合−>
メキシコの場合、植民地時代を通してインディオは迫害されてきました。そのインディオたちが政治の中で脚光を浴びるのはメキシコ革命後です。マヌエル・ガミオが、まずメスティソ(白人とスペイン人の混血)の文化を高く評価しました。その後を受けて、初代文部大臣になったバスコンセロスが、「先住民文化のもとに、民族、言語、文化を統一すべきである」と唱えました。すなわち、インディオをメキシコの国民意識のシンボルとして評価したわけです。そして、インディオの国民社会への統合化政策が展開されていきます。時間の関係で、この章については割愛させていただきます。
<おわりに−グローバル化時代の先住民と言語・文化−>
皆さんご存知のように、今日はグローバル化時代と呼ばれていて、経済面においては「新自由主義政策」が展開されています。1994年にカナダ、アメリカ、メキシコの三国間で北米自由貿易協定(NAFTA)が結ばれました。その結果、競争力のない都市の中小企業、あるいは零細な地方の農業は大きな打撃を受けました。貧富の格差が一段と大きくなり、農村からの人口流出が一段と加速したのです。また、アジアからの安価な工業製品や遺伝子組み替えトウモロコシの流入は、農村社会の崩壊を加速する一方でした。
さて、そうした農村部から溢れた人たちが、当然のことながら都市へと移動していきます。これは人口移動の国際化の前段階で、1950年から80年代がその時期にあたります。都市に流れ込んだ農村の先住民、あるいは農民たちはスラムを形成すると同時に、インフォーマル・セクターという経済領域に滞留します。ところが90年代に入ると、グローバル化の波に押され、国境を越えて移動します。その移動によってアメリカ国内のヒスパニック人口が急増し、あるいは、日系出稼ぎ労働者が、とりわけ愛知県を中心とした東海地方で急激に増加したわけです。今日では、メキシコからは国境を越えてアメリカへどんどん入って行き、南米からはブラジルやペルーの日系の人たちが日本に来ています。このように、国際間の人口移動がますます加速されています。
最後に、20世紀は「民族の時代」と言われましたが、21世紀は様々な形で表れた民族間の軋轢(あつれき)をいかに解決し、先住民の人たち、あるいは移動してきた人たちといかに共生を図るかというのが私たちに課された課題ではないでしょうか。一言では解決の糸口は掴めないと思いますが、これからそれを模索していく時期が今日ではないかと思います。