<はじめに>
 |
|
堀田英夫先生 |
下の図を見てください。分かりづらいですが、色のついているところがスペイン語圏の範囲です。スペイン語というと、まずスペインの言葉と思いますが、人口から見るとメキシコやコロンビアの方が多いです。その次にスペイン、アルゼンチン、アメリカ合衆国と続きます。左の図の最後に赤道ギネアという国が書いてあります。この国は、アフリカにある小さな国で人口的にはそんなに多くありませんが、元々スペインの植民地だったということもあって、スペイン語が公用語になっています。
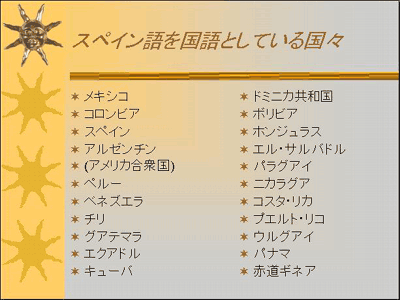 | 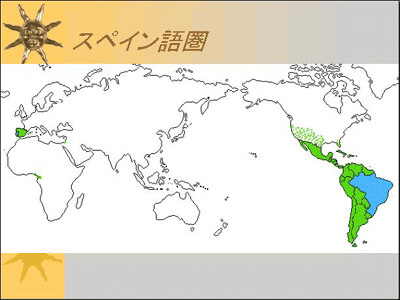 |
<スペイン語の成長>
スペイン語は口語ラテン語から成長し、カスティリャ王国で使われていた言葉で、アラビア語やいくつかの言語の影響を受けて、現在のスペイン語になりました。イベリア半島のほとんどはローマに占領されていましたが、711年に北アフリカからイスラム教徒が押しかけ、大部分をイスラム教徒に占領されたのです。そのため、キリスト教徒たちは北の方に追いやられて、そこにいくつかの王国ができました。そして、カスティリャ王国が時代と共に国土回復戦争(レコンキスタ)で南に領土を広げていき、カスティリャのイサベル女王とアルゴンのフェルナンド王が結婚してスペインを統一したというのがスペインの歴史です。それとともに、カスティリャ語(スペイン語)がイベリア半島の言語になりました。
<スペインの1492年>
1492年という年は今のスペイン語にとっても、あるいは世界史的に見ても非常に重要な年ですので、言葉に関することを中心に主に3つお話します。
まず、グラナダ王国を征服したということがあります。グラナダは最後のイスラム教徒の国で、アルハンブラ宮殿があることで有名なところです。イサベル女王率いるカスティリャ軍が1492年の1月2日にアルハンブラ宮殿に入城し、イスラム教徒の王様が追放されました。それから同じ年に、ユダヤ人追放令をイサベル女王が出しています。これによって政治、軍事、それから宗教すなわちカトリック教による国家統一が行われました。その後、ユダヤ教徒でカトリックに改宗した人たちが、文学や政治など非常にいろいろな面で重要な役割を果たします。そして国外に逃れたユダヤ人はバルカン半島などに移住し、後にイスラエルに行ったので、イスラエルにもスペイン語が残っているわけです。
そして、1492年が言葉の上で非常に重要なのは、ネブリハという人が『カスティリャ語文法』を出版していることです。これは史上最初の日常語文法です。現在では、それぞれの言語に文法書があるのは当たり前のことかもしれませんが、中世の頃は文法というとラテン語の文法しかありませんでした。日本語で考えてもらえば分かりますが、日本語をどういうふうに喋るかというために日本語の文法を見ようという人は、ほとんどいないと思います。しかし、ネブリハはスペイン語を普段喋っているのに、スペイン語の文法書を書いたということで歴史上、画期的なことだったのです。この文法書を出版した目的は文法書の前書きにも書いてありますが、言語による国家統一です。ネブリハは当時、スペイン帝国が一番盛んな時であると思い、今スペイン語を固定しておけば後の時代にも読んで理解してもらえると思ったのです。また、ラテン語を学習する人のために、前もってスペイン語を文法的に勉強すればやりやすいということも書いています。実は、ネブリハはラテン語の先生でした。ラテン語によるラテン語入門書を書いてイサベル女王に献呈していますが、女王はラテン語を勉強するのにラテン語では読めないと言って、ネブリハはスペイン語訳して再び献上しています。その他にも、ラテン語カスティリャ語辞書、史上初のスペイン語引き辞書であるスペイン語ラテン語辞書も出版しています。
それから1492年で誰でも思うことは、コロンブスの新世界への到達です。僕にとって興味深いのは、インディオたちとのコミュニケーションは可能だったのかということです。『コロンブス航海誌』によると、どうやら通訳を使ったり、贈り物や身振りなどをしてコミュニケーションを図ったようです。しかし実際のところ、あまりコミュニケーションは取れていませんでした。身振りで聞いて分かったつもりにはなっていても、コロンブス自身はジパングに着いていないことを理解できていないからです。その他にも、この頃のポルトガルやスペインの探検隊は先住民を捕まえて自分たちの国へ連れて行き、言葉をその者たちに覚えさせて、次に来る時に通訳に使うということをやっていたようです。これはスペイン人の名誉のために言っておきますが、しばらく後にスペイン人自身がこういう行為は人間の法に反することであると糾弾しています。最初はインディオを使ってお金儲けをしていたバルトロメ・デ・ラス・カサスというスペインの聖職者が、これは人間の法に反するということに気付いて1514年に回心し、その後はインディオの自由と生存権を守るために精力的に活動しました。また、バルトロメ・デ・ラス・カサスがスペイン人の行為を告発したことを、後の時代にアメリカ合衆国や他の国がスペインと戦争をする理由として利用したようです。つまり、スペイン人はこんな悪いことをするからスペインと戦うのは正しいのだと。しかし、その頃スペイン人自身は、こうした行為に対する判断をちゃんとしていたということをここで言っておきます。
<征服戦争における言葉の戦い>
アステカ王国征服の時に、なぜ数万人のインディオ兵は数百人のスペイン兵に負けてしまったのでしょうか。よく言われることは、軍事的な理由です。インディオは木の棍棒に黒曜石の刃を付けた剣を使っていましたが、スペイン人は鋼鉄の剣や銃、甲冑、馬を持っていました。それから、アステカ側は生贄の捕虜を得るため生けどりにしようとする戦争でしたが、スペイン人は反抗する者は切り殺していました。つまり、戦いの仕方が違っていたわけです。それから、天然痘などの病気が旧大陸からもたらされたということも挙げられます。スペイン人は免疫がありますが、インディオは免疫がないのですぐ倒れ、アステカの王様も病気で倒れた人がいたということです。
ブルガリア生まれの構造主義文学者、ツヴェタン・トドロフは次のように言っています。
「インディオはとくに人間対世界のコミュニケーションに努め、スペイン人は人間対人間のコミュニケーションに努めている」
世界というのは、自然界を含めた人間を取り巻く全体ということで、神様や自然現象なども含んで何かそういうものとコミュニケーションしようとしていたわけです。
「アステカ人にとって、あたかも記号は他者を操るための武器ではなく、それが指示する世界から記号が自動的に、
必然的に流れ出すかのようにすべては展開する」
ツヴェタン・トドロフ(1986)『他者の記号学/アメリカ大陸の征服』法政大学出版局、(Paris,1982)
記号というのは、言葉と置き換えてもらってもいいかもしれません。要するに、運命は定まっているとか、あるいは占いによって自分の行動を律するということが負けた理由だということです。
また、スペイン側は通訳を使って相手に言葉で意志を伝えることができ、あるいは相手の言っていることを聞くことができました。マヤ語スペイン語の通訳をしたスペイン人のヘロニモ・デ・アギラ−ル、ナワトル語マヤ語の通訳をしたインディオのマリンチェ、こういった通訳の存在が非常に大きいと僕自身は見ています。アステカ王国に貢物を捧げていたトトナコ人も言葉によって味方に付けることができました。アステカの圧政から守ってやると言ってアステカ人使者を捕まえさせ、一方でスペイン人はその使者を逃がします。トトナコ人には捕虜を逃がしたとして叱責し、スペイン側に付かざるを得なくさせたのです。つまり、両方に別々のことを言って情報操作をするわけです。そういう情報操作ができたのは通訳のおかげだろうと思われます。
そういったことによってスペインはアステカ王国を征服できたのですが、ラテンアメリカには多くのインディオが居住し続けたのに、なぜスペイン語が普及したのでしょうか。スペイン王家はスペイン語普及の命令を何度も出しました。しかし、スペイン人入植者はインディオを労働力として使うだけでスペイン語の普及には熱心でなく、宣教師たちもキリスト教布教が目的なので、自分達の方がインディオのことばを習得し、スペイン語を必要としなかったのです。ただ、インディオ自身が自分たちを支配する人たちの言葉を学ばないと生きてはいけない、あるいは少しでも良い暮らしをするためにということで、スペイン語の教育をしてほしいという請願書を出しています。そこに、スペイン語化の理由があるのではないかと思います。
<スペイン語の拡大>
19世紀初頭には中南米諸国が独立し、いくつかの経済発展がありました。例えば、冷凍船の発明によってアルゼンチンの肉をヨーロッパに売ったり、メキシコはサイザル麻の生産地として繁栄します。政治的には、スペイン語の国の数が多いので、国際連合や米州機構において公用語として使われるということがあります。それから、皆さんご存知のラテン音楽・ラテンアメリカ文学のブームや、美術・建築においてもスペイン語圏は非常に豊かな文化を持っています。そして、アメリカ合衆国のヒスパニックの増加、EUの一員であるスペインの経済発展、日本でも1989年の出入国管理法改正による、在留日系ペルー人(ブラジル人)の増加、日本とメキシコとの自由貿易協定などによりスペイン語の重要性が増しています。
最後に申し上げたいことは、いろいろな国々との交流は日本にとっても非常に重要だということです。確かに、英語はグローバル化という面で必要な言語です。しかし、世界中には多用な言語があります。ですから、英語の他にもう1つ何か勉強した方がいいのではないかということで話を終わりにしたいと思います。