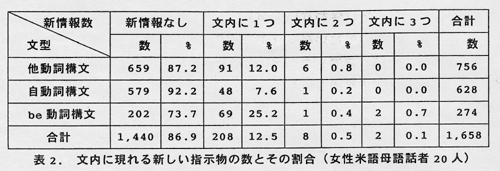2.一つの文の中に、新情報は一つが限度
次に、新情報が文の中にいくつ入るのかを考えてみます。他動詞の文であれば「〇〇が○○を」と名詞の入る位置が2つはあります。さらに場所などを示す前置詞句を含めればさらに新情報を押し込めることが可能なはずです。しかし、実際の語りを調べてみると、そういったものはあまり出てきていません(表2を参照)。入れる場所はあっても、新情報はせいぜい1つしか入れていないのです。文の中で3つも新情報が出てくるような例というのは、A and Bみたいに接続詞で結んでしまった場合です。そういったものを除くと、基本的には多くて1つしか出てきていないということです。これは、ほとんどの語り手に共通しています。いろいろな説明は可能かもしれませんが、私が考えていることは、これは自発的な語りであるということと関連しています。話の最初は少しは準備ができるので、頭の中で文を組み立てて作ることはできるかもしれませんが、しゃべりだすとそういった余裕はありません。その中で相手に何かを伝えていこうとした場合に、1つの文の中に2つ以上同時に新情報をつめこむのは非常に大変な作業です。それは聞き手にとっても同じことです。そのため、文の最初の位置には既に話題になったものが来やすいと考えられます。あらかじめ了解された事柄が最初に出てきて、それを元にして新情報を付け加えるというパターンになっています。ですから、コミュニケーション上の暗黙のルールみたいなものがあって、分かっているものを元にしてそこに付け加える形で新情報を提供しているのではないかということです。このことと、一つの文の中で複数の新情報を同時には処理できないということが、表2の結果に反映していると考えられます。