1 家庭と家庭教育
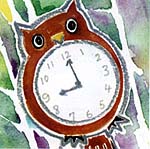 「家庭」という言葉が一般に使われるようになったのは比較的新しく、それまでは「家族」という言葉が一般的であったようです。家族というのは、夫婦を中心とし、親子きょうだいなどの近親者で構成されており、お互いの愛情や家族意識によって結ばれ、泣いたり笑ったり、共に生活する人の集まりを意味します。そして、この家族が、共に生活する場所を「家庭」というのです。したがって、家族という時には人が中心となり、家庭というときには場所、特に家の中を指す場合が多いようです。
「家庭」という言葉が一般に使われるようになったのは比較的新しく、それまでは「家族」という言葉が一般的であったようです。家族というのは、夫婦を中心とし、親子きょうだいなどの近親者で構成されており、お互いの愛情や家族意識によって結ばれ、泣いたり笑ったり、共に生活する人の集まりを意味します。そして、この家族が、共に生活する場所を「家庭」というのです。したがって、家族という時には人が中心となり、家庭というときには場所、特に家の中を指す場合が多いようです。
家庭教育というのは、主として家庭の中で親が子どもに対して行う教育です。生まれたときから日曜も休日もなく、親と子の細やかな接触を通して行われる教育です。一定の資格を持つ専門家の先生が行う学校の教育と比べると、家庭教育の内容は非常に幅広いものがあります。
2 三つ子の魂百まで
幼児期は一番物事を覚える時です。「三つ子の魂百まで」というように、この時期覚えたことは一生忘れないと言われます。
特に基本的生活習慣の形成は、そのまま性格形成につながると言われます。良い習慣の形成はよい性格を育て、悪い習慣の形成は悪い性格を育てるとも考えられます。
また、子どもの発達の過程には、ある時期には身に付けやすいけれど、その時期を逃すと意欲を失ったり消極的になったりして身に付きにくくなることもあります。したがって、食事、排せつ、睡眠などの生活のリズムを子どもの発達に合わせて整えることも、この時期大切なことです。
3 子どもの好奇心・関心
育児には二つのことが含まれます。子どもを保護することと育てることです。「育」という字は「巣立つ」に通じ、さらに子どもが社会人として自立をしていくのを促進するという意味を持っています。社会生活が可能になるよう、最低限の基本、きまりを身に付けさせることも大切です。
子どもがいろいろなことを身に付けていく基本は、好奇心とか関心による行動です。大人がしていることのまねをするのもその一つです。はしやスプーンを使うのもトイレに行くのも、あいさつをするのも、みんな好きな人(おもに父親・母親)がしていることをまねて身に付けていくのです。「子どもは親の鏡」と言われるのもそのためです。子どもは、自分の好きな人、愛着を持っている人のすることをそのまま、自分の中に取り込んでいきます。
その意味でも親自身の在り方、生活の仕方が非常に重要になります。家庭教育の基本は、まず何よりも家庭が家庭生活(人間としての暮らし)の条件を満たしていることです。