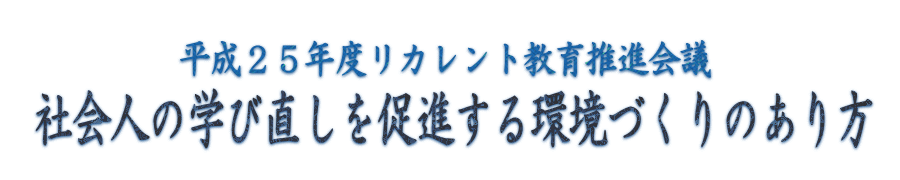
目次へ・1へもどる
2 行政と複数の高等教育機関との連携
講師:大学コンソーシアムせと協議会 会長 木村光伸 氏(名古屋学院大学リハビリテーション学部長)
(1)「リカレント教育」「生涯学習」について
 大学コンソーシアムせとの木村です。名古屋学院大学の教授も勤めております。今日は行政と複数の高等教育機関との連携というタイトルで、お話をします。
大学コンソーシアムせとの木村です。名古屋学院大学の教授も勤めております。今日は行政と複数の高等教育機関との連携というタイトルで、お話をします。
ここ十年くらい、生涯学習は疲労困憊を続けています。大学はどんなものを提供すべきか、よくわからない。一方で、自治体ではいろんな講座をやらなければいけないが、何をすべきか、わからない。大学コンソーシアムせとでは瀬戸市という地で2000年頃から、この課題に真剣に取り組んできました。そもそも「リカレント教育」とは何でしょうか、あるいは「生涯学習」とは何でしょうか。
瀬戸市役所に「交流学び課」が設置された経緯から、この課題に対する1つの答えをお話しします。瀬戸市役所の「交流学び課」は市長部局に設置されているということが非常に重要な点です。「生涯学習」という言葉は「社会教育」という言葉に代わって登場しました。この変化は学びの主体が変化したことに伴うものでした。行政が市民に「生涯学習」を与えるのではなく、「市民が主体的に学ぶ場」を提供するという方向に変化したということです。つまり「市民が主体的に学ぶ場」を望んだときに上手にマッチングすれば良いのです。なかなか、そこまで市民の立場で考える自治体はなく、瀬戸市も例外ではありませんでした。瀬戸市役所はある時から学びのスタイルをすべて変えるという取組をはじめました。現在では、講師となった市民が学びたい市民に講座を提供するという「学び講座」を100講座ほど開講しています。これは岐阜県多治見市での取組を参考にしました。
また瀬戸市役所では公民館を再構築しつつ実質的な地域活動の場に転換しています。現在の新しい生涯学習をベースにした公民館活動を促進するため、公民館改革を実施しています。公民館がこれまで担ってきた活動はもちろん、社会福祉協議会、まちづくり協議会や婦人会をはじめ市民が一丸となって地域活動を推進する場としての役割を公民館が果たせるようにしたいと考えています。現在では、瀬戸市長の主導で設立された市民活動支援室と大学コンソーシアムせとが共同して、この取組を進めています。
リカレント教育とはそもそもOECDが提唱した概念です。すべての市民が反復・循環・回帰、つまり繰り返し自分が望んだときに自分が望む学習をする場が保証されているということでした。しかし実際には日本において市民は生涯学習の概念を誰かが与えるものを享受するものとして捉えてきました。そうではなく本当の意味で生涯学習について市民が人材形成の場として捉え、与える側は自己発展としての生涯学習の機会を提供すると捉えていく必要があります。
(2)大学コンソーシアムせとの設立経緯
高等教育機関の役割について話します。現在、大学コンソーシアムせとは5大学で運営しています。もともと6大学でしたが、1つの大学は学生がすぐに瀬戸に集まれないという地理的な要因で抜けました。大学では様々な広報活動の一環として、地域連携活動を行っています。大学における教育研究が地域でどのような役割を果たしていけるかが、とても重要です。しかし大学の使命として、教育、研究と地域貢献が正三角形と捉えられがちですが、教育と研究があるからこそ、地域貢献を果たしていくことができるのです。そのことを高等教育機関は認識すべきです。地域や行政の側は高等教育機関ともっと連携し、活用して良いと思います。そのためには常日頃から、お互いのコミュニケーションを密にしておく必要があります。
大学コンソーシアムせとが正式に立ち上がったのは2004年ですが、スタート自体は2000年です。2000年12月に2005年の愛知万博開催に向けて瀬戸市長から私に名鉄尾張瀬戸駅前の再開発を実施するにあたって駅前ビル構想の策定をして欲しいと依頼がありました。当時の名鉄尾張瀬戸駅前には古い町並みが取り壊されて広大な空き地だけが拡がっていました。この地を瀬戸市で一番主要なランドマークにするために市民が望むものをつくる必要がありました。市民も観光客も集まることができ、そこから街中へ出発できるような施設が必要だと考えました。再開発計画を策定するために、検討チームを立ち上げました。この検討チームは名古屋学院大学と南山大学の若手教員2名ずつ、学部学生数名、金城学院大学大学院生1名、瀬戸市役所の若手職員2名、商店街の住民で構成されていました。瀬戸市に必要なものについて議論を深めていき、取捨選択をした結果、つくりあげたのが「パルティせと」です。瀬戸市には1300年の歴史や焼き物の町としての伝統があると言われていましたが、愛知万博を契機として文化都市、産業都市、産業観光都市を目指す方向に転換していこうとしていました。そのときに参加してくれたのが、南山大学、愛知工業大学、金城学院大学、名古屋産業大学、名古屋学院大学です。日本に数多くある大学コンソーシアムの中でも最小の部類に属するでしょう。現在では、瀬戸市役所の職員2名、非常勤1名(大学コンソーシアムせとで雇用)だけで、事務局を運営しています。
(3)大学コンソーシアムせとの現状と今後の展望
大学コンソーシアムせとは「生涯学習」のための組織ではなく、行政・大学・市民が連携して推進している「まちづくり」のための組織です。大学コンソーシアムせとは「パルティせと」を拠点にしていますが、3階にある市民窓口の一角に事務局があるだけです。大学コンソーシアムせととしては、講座などを実施する会議室を所有しているわけではなく、講座の開講時に会議室を借りるという形をとっています。小さな自治体で専用施設を有し、専属で人員を配し、大学をまとめていくことは困難でしょう。大学コンソーシアムせとは1つのシステムとして行政や大学、市民がそれぞれの役割を担っていくことで、回り続けていくのです。
大学コンソーシアムせとの活動について紹介します。
①「大学別テーマ講演会」:それぞれの大学が独自のテーマを出して講演会を開催。
②「カレッジ講座」:いくつかの大学が2つずつ講座を提供して開講。
「パルティせと」と同時期につくられたのが、博物館やホールを有する「瀬戸蔵」です。年に1回、この施設で他大学の学生との交流を目的とした5大学合同大学祭を6月に開催しています。最近では、学生同士の交流はもちろん市民と学生との交流の場となっています。また瀬戸地域近郊駅伝大会が12月に開催されており、大学コンソーシアムせととして10チームくらい参加しています。こちらも市民と学生との交流を通じて市民活動を活性化するお手伝いをしています。
リカレント教育の推進に向けて大学は何ができるでしょうか。大学コンソーシアムせとは瀬戸市内の小中学校で教育指導や学習支援、講師派遣という活動を実施しています。学校からの要望と大学ができることを上手くマッチングすればよいという考えで進めています。また市民にとって「身近な大学」となるために様々なイベントに積極的に参加するようにしています。そのような活動を地道に積み重ねることで大学コンソーシアムせとの認知度を上げていき、大学の公開講座への参加に結びついていくことが目標です。さらに瀬戸市役所の様々な事業のうち、いくつかを大学コンソーシアムせとと共同で推進したいと瀬戸市役所から依頼があります。逆に大学からも行政と共同してプロジェクトを推進したいと依頼しています。こういった活動を通じて、新しいネットワークが形成されていくこともあります。
リカレント教育で必要なことは、1人1人の生活目標をその人の目線で実現させてあげることができるかどうか、です。そのためにはその人が望めばいつでも教育に参加することができる、学習機会を自分のものにすることができる仕組みをつくっていく必要があります。そのためにも行政と大学、地域がコミュニケーションを密にしていく必要があると考えています。
ご静聴ありがとうございました。