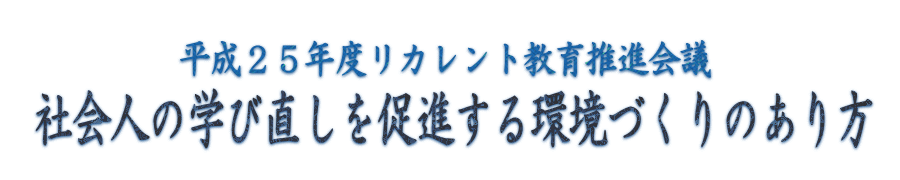
目次へ・2へすすむ
1 一元的なリカレント教育関連講座の提供方法の確立
(1)「公益財団法人大学コンソーシアム京都の概要」
講師:公益財団法人大学コンソーシアム京都 教育事業部次長 徳永智史 氏
公益財団法人大学コンソーシアム京都の設立経緯
 皆さま、改めましてこんにちは。大学コンソーシアム京都(以下「財団」という)の徳永です。本日は、「一元的なリカレント教育の確立」というテーマで、私と菅尾で財団の概要と財団が実施している生涯学習についてお話しします。私は財団で教育事業部に所属しています。本務校の京都産業大学から公益財団法人財団に専従で出向しています。
皆さま、改めましてこんにちは。大学コンソーシアム京都(以下「財団」という)の徳永です。本日は、「一元的なリカレント教育の確立」というテーマで、私と菅尾で財団の概要と財団が実施している生涯学習についてお話しします。私は財団で教育事業部に所属しています。本務校の京都産業大学から公益財団法人財団に専従で出向しています。
18歳人口の減少もありますので、大学も受験生獲得のことも念頭に置いています。なおかつ高校生はもちろん保護者からも大学に対する様々なニーズが質的にも量的にも大きくなってきているという状況もあります。特に最近ですとキャリア教育へのニーズが増大しています。財団では「大学の町・京都、学生の町・京都」と言っていますが、1980年代から90年代にかけて、大規模な大学が京都から出て行きました。このときの「京都」の定義としては市か、府なのか、難しい部分もありますが、同志社大学や立命館大学をはじめとする大規模な大学が京都市内から市外へ、府外へ出て行くという動きがありました。最近の京都を取り巻く状況としては、用地の確保ができたため、大規模な大学が京都に戻ってきています。
こうした京都に住む大学生人口流出という問題に京都市と大学が共同で取り組もうということで「大学のまち・大学センター」という構想が出てきました。財団は中長期の計画に沿って事業を進めています。1994年に中長期の計画が完成するとともに、現在の財団の前進となる「京都・大学センター」が発足しました。1994年から2003年までの第一ステージ期に基盤整備を推進し、2004年から2008年までの第二ステージ期には国際規格において最も優れた高等教育を目指して事業を推進しました。今年は2009年から2013年までの第三ステージ期の最後の年です。来年から第四ステージが始まります。現在は第四ステージ期の計画を策定中です。これまで数的・量的に事業を拡大してきた結果、評価できる点もありましたが、問題点も表面化してきています。この状況を踏まえて、第四ステージ期の計画では、講座の取捨選択という方向になると考えています。
公益財団法人大学コンソーシアム京都の概要
財団の概念・理念・目的についてお話しします。
目的①「京都地域を中心に大学間連携と相互協力を図り、加盟する大学・短期大学の教育・学術研究水準の向上を目指すとともに、学生の成長を促進するための学生支援、大学の国際化を推進するための国際連携・国際交流等の充実に努める。」
目的②「地域社会、行政及び産業界との連携を促進し、地域の発展と活性化に努め、京都地域を中心とした高等教育の発展と国際社会をリードする人材の育成を目指す。」
なお財団は加盟大学の上位組織ではないということを申し添えておきます。各大学の持ち味や個性を生かして共同していくための組織です。
財団の沿革を見ていきます。
1994 単位互換事業開始
1995 第1回FDフォーラム
1997 シティカレッジ事業開始
2010 公益財団法人移行認定
財団の運営体制を見ます。事務局職員、教員など約300人が関わっている組織です。事務局を運営する職員が約50名います。その内訳として事務局長を含めて約半数の職員が加盟校からの出向職員です。残りの半分が専門職員、有期雇用の職員です。臨時職員、アルバイトも数名います。独自のテーマを調査研究する専門研究員も約2名おります。財団の意思決定をするための各種委員会は加盟校の教員で構成されています。
財団の事務局は、「キャンパスプラザ京都」という建物に置かれています。正式名称は「京都市大学のまち交流センター」と言います。京都市の建物です。この施設はもともと京都市が建てたので、放送大学も入っていたりします。財団はキャンパスプラザ京都の指定管理者として、京都市から委託を受けて貸館業務や施設の維持管理を行っています。京都市からの財政面での援助もあります。
財団の加盟組織については、京都地域の約50の国立・公立・私立の大学、短期大学に加え、地方公共団体や経済団体、賛助会員で構成されています。
財団の意思決定については、事務局での会議で検討したのち教員を含めた会議、運営委員会、評議委員会、理事会を経て決定されます。役員には加盟校の学長や総長が、委員には加盟校の副学長や部局の部長が就任しています。
公益財団法人大学コンソーシアム京都の事業
財団の事業について見ていきます。
- 単位互換事業:大学間で単位を認定するというもの。
- 生涯学習事業「京カレッジ」
- インターンシップ事業:各大学でも独自に実施しているため需要は減少しつつあります。
- 京都学生祭典:大学の枠を超えた大学祭です。歌手の倉木麻衣さんに出演していただいたこともあります。
最近ではダンスが大学祭の主流になっています。 - 京都国際学生映画祭:映画のコンテストです。
- 京都学生芸術普及事業:京都には芸術大学も多く、発表の場を提供しています。
③ 高大連携事業
高大接続事業、京都高大連携研究協議会事業、共同広報事業を実施しています。
④ 高等教育研究推進事業
- FD関係事業:教員の能力アップを図っています。
- SD関係事業:大学職員の能力アップを図っています。たとえば大学職員の新人研修を財団として合同で実施するということもあります。
- 都市政策研究推進事業:都市が抱える問題解決策を研究する事業です。
- 国際連携事業:学生の短期海外留学の実習プログラムです。学生の短期海外留学プログラムを財団として単位互換制度を利用しながら合同で実施していくという事業です。
⑤ 総務・広報
全国大学コンソーシアム協議会の事務局も担っています。
これまで財団の概要を話しました。次は菅尾から生涯学習について話します。
(2)「生涯学習事業(京カレッジ)の現状と課題」
講師:公益財団法人大学コンソーシアム京都 教育事業部主幹 菅尾博之 氏
生涯学習事業(京カレッジ)の概要
財団の菅尾が生涯学習事業「京カレッジ」についてお話しします。
「みやこの表象」について話します。これは10回連続の講演で、財団が提供している唯一の講座になります。毎年テーマを選定して、今年度は「みやこの表象」というテーマで開講しています。10回のうち前期と後期の最終日に、実地講座を取り入れています。
まず京カレッジの概要について話していきます。京カレッジは大学講義(大学の正規科目)、市民教養講座(大学が実施する1回限りの無料講座等)、キャリアアップ講座(語学講座や資格取得に関する講座)、京都力養成コースの4つのカテゴリーから形成されています。京都力養成コースでは、財団から加盟校に対して京都地域で活躍する人材を育成するため、社会人に向けた京都らしい特色ある科目を募集しています。このコースについては提供校に科目開設補助金を拠出しています。
京カレッジの特徴は加盟校から提供を受けた科目を一冊の募集ガイドとしてまとめている点にあります。複数の大学へ出願する場合についても、財団への一括出願だけで済むという特徴もあります。費用についても各加盟校が定めている費用だけ負担すれば良く、財団への手数料等を負担する必要はありません。図書館をはじめとする加盟校の施設についても京カレッジ生の学生証があれば、各加盟校が許可する範囲内で利用できます。
京カレッジの科目の受講場所は約100科目がキャンパスプラザ京都で、残りの300科目が各加盟校のキャンパスとなっています。
京カレッジ科目の出願は財団で書類を受付け・仕分けをしてから、各加盟校に送付しています。各加盟校に書類が到着してからは、出願者本人と直接連絡を取ります。
出願資格・期間・方法についてです。出願資格については、大学講義については大学入学資格が必要ですが、その他は特に資格は必要ありません。
前期の出願受付期間は3月9日から23日。受付方法は郵送、持参、ウェブです。ウェブ出願の場合、証明書類や写真は郵送してもらう必要があるという問題が生じています。
生涯学習事業(京カレッジ)の現状と課題
京カレッジの現状について話します。現在の提供科目数は約400科目です。財団実施の単位互換科目と大部分が重複していますが、約半分の講座では受講生は1人もいません。
出願者の属性としては、男女比は同数くらいで60代以上が約6割を占めています。大学提供科目が主なので土日の開講科目が少なく、60代以上の出願者が増加しています。
1人あたりの出願科目数ですが、1科目だけという方が44.2%を占めています。複数の大学に一度に出願できるという京カレッジのメリットが生かしきれていないのが現状です。
京カレッジのカテゴリーごとに現状を見ます。大学講義のうち約6割の科目では出願者が1人もいませんでした。大学講義としてeラーニングを実施していますが、開設科目の半数でしか受講希望者が集まりませんでした。市民教養講座では28科目に対して248名の出願者がおり、人気を集めています。無料講座が多くあるからかもしれません。キャリアアップ講座のうち半数近くの科目では出願者が1人も集まりませんでした。京都力養成コースについては定員オーバーとなってしまったため、受講できない人も現れるほど申込みが殺到しています。無料講座も多く、回数も4,5回と手頃な講座が多いからかもしれません。
京カレッジの課題をいくつか挙げていきます。京カレッジが大学からの提供科目で構成されているという点に起因する課題です。
- 科目の提供方法:大学からの提供科目の選択については大学に一任しています。財団からも提供科目の内容について強い働きかけはしていません。財団としてコーディネートしていく必要があるとも考えています。
- 出願の手続き:出願者は各加盟校への必要書類を提出するとともに、京カレッジにも同種の必要書類を提出しています。なかなか一元的な手続きは難しいという現状です。
- 京カレッジとして出願するメリットが実感しにくい:最近はどこの大学図書館でも一般の方に開放していますし、京カレッジの会員証を持っていても自大学の科目等履修生にのみ貸出を認めている大学もあります。 加盟校の側からは出願者数が増える、広報効果があるという声を頂いてはいます。
出願者の実情を毎年実施しているアンケートを活用して今まで以上に把握する必要があると考えています。
ご静聴ありがとうございました。