(8)障害者施策の歩み
ア 社会のバリアフリー化戦後、我が国では障害者に対するさまざまな施策が施行されてきました。昭和24年の身体障害者福祉法、昭和25年の精神衛生法(平成7年の精神障害者福祉法)、昭和35年の精神薄弱者福祉法(平成10年の知的障害者福祉法)などが立法化されました。しかし、これらの法律は、障害のみに視点をあて、障害の種別や程度によって援助を定めたものであり、障害者の人間性や人権を無視したに等しいものでした。そして、平成5年に障害者基本法が成立し、やっと法律上では障害者が社会を構成する一人として認められるようになったのです。平成14年、内閣は障害者基本計画を策定し、障害者も社会構成員の一人として、社会への参加・参画ができるようにするため、社会のバリアフリー化を推進することを決定したのです。
イ 社会生活を営むことができるための支援
 平成5年12月に成立した障害者基本法では、一つにリハビリテーションの理念に基づく保健施設、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進を重点項目と定め、障害者の雇用促進を図りました。二つ目には、ノーマライゼーションの理念に基づいた社会のバリアフリー化の推進を挙げ、これら二つを基本理念とした施策が、各県で行われることになったのです。愛知県では、平成5年から12年までの「あいち8カ年福祉戦略(愛フルプラン)」、平成13年から22年までの「21世紀あいち福祉ビジョン」が策定され、障害者が人として尊重され、社会生活を営むことができるための支援が続けられています。
平成5年12月に成立した障害者基本法では、一つにリハビリテーションの理念に基づく保健施設、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進を重点項目と定め、障害者の雇用促進を図りました。二つ目には、ノーマライゼーションの理念に基づいた社会のバリアフリー化の推進を挙げ、これら二つを基本理念とした施策が、各県で行われることになったのです。愛知県では、平成5年から12年までの「あいち8カ年福祉戦略(愛フルプラン)」、平成13年から22年までの「21世紀あいち福祉ビジョン」が策定され、障害者が人として尊重され、社会生活を営むことができるための支援が続けられています。
ウ 障害者自立支援法
平成17年に「障害者自立支援法」が制定されました。これは、これまで障害種別ごとにされてきた公費負担、医療、福祉サービス等を共通の制度の下で一元的に提供する法律です。そこには、「障害者がもっと働ける社会を作る」ことや、「限られた社会資源を活用できる規制緩和」これは、例えば「少子化で空いた学校の教室を障害者のために開放する」といったことで障害者の利便性を向上させる制度なのですが、一方で「福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う」など、障害者の負担増に繋がるものもあるのです。
(9)障害者を異質なものとしていませんか?
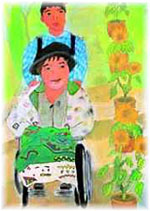 私たちは、自分自身の心の中に障害者を異質なものを持つ人間として、排除し、差別する気持ちがありはしないか、自問することが最も大切です。もし、障害者を排除する心があったら、それは人権侵害にあたることを認識すべきです。障害者は、「地域で普通の暮らしがしたい」、「自分の意思であちこち出かけてみたい」、「旅行もしてみたい」と願っているのです。これは、人間としてあたりまえのことです。この「あたりまえのこと」が、障害者に許されない社会は、人権社会とは言えないのです。
私たちは、自分自身の心の中に障害者を異質なものを持つ人間として、排除し、差別する気持ちがありはしないか、自問することが最も大切です。もし、障害者を排除する心があったら、それは人権侵害にあたることを認識すべきです。障害者は、「地域で普通の暮らしがしたい」、「自分の意思であちこち出かけてみたい」、「旅行もしてみたい」と願っているのです。これは、人間としてあたりまえのことです。この「あたりまえのこと」が、障害者に許されない社会は、人権社会とは言えないのです。