 |
|
佐藤徳潤先生 |
<ロマンス諸語について>
ロマンス諸語はいくつかの分類の学説がありますが、まず東側と西側に大きく分かれます。それぞれの語系が以下に書いてあるとおりです。
(東ロマニア)
1.バルカン・ロマンス語系:ルーマニア語、メグレノ・ルーマニア語、ア・ルーマニア語、イストロ・ルーマニア語、ダルマチア語
2.イタロ・ロマンス語系:イタリア語、サルディニア語
(西ロマニア)
1.レト・ロマンス語系:フリウリ語、ドロミテ・ラディン語(ドロミテ語)、ロマンシュ語
2.ガロ・ロマンス語系:フランス語、フランコ・プロヴァンス語、プロヴァンス語(オック語)
3.ヒスパノ・ロマンス語(イベロ・ロマンス語)系:カタロニア語、スペイン語(カスティリア語)、ポルトガル語、ガリシア語
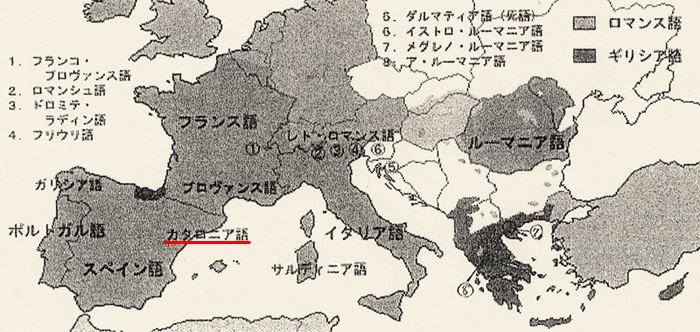 |
スペイン語とカタロニア語は西側に属するものです。地図をみると、フランスの辺りにプロヴァンス語(最近はオック語と言います)と書かれていて、その下に国境線があり、ここにピレネー山脈があります。そのすぐ下にカタロニア語と書かれていて、そこに今で言うカタロニア語圏があります。その他にスペイン語とガリシア語がスペインという国の中にあるロマンス諸語です。
基数詞の比較を少しだけみていこうと思います。以下に1と2と5を挙げました。ラテン語からルーマニア語までがロマンス諸語で、右の3つがそれ以外の言語です。その語系の母音あるいは子音をみると、明らかにロマンス諸語というのは音が同じになっています。例えば2をみると、dの音で始まっています。このように言語の音の対比から系統的なものがみえてくることがあります。ただ5では音の違いがみられます。
| ラテン語 | スペイン語 | カタロニア語 | ポルトガル語 | フランス語 | イタリア語 | ルーマニア語 | スウェーデン語 | デンマーク語 | ドイツ語 | |
| 1 | unus | uno | un | um | un | uno | unu | en | én | eins |
| 2 | duo | dos | dos | dois | deux | due | doi | tvá | to | zwei |
| 5 | quinque | cinco | cinc | cinco | cinq | cinque | cinci | fem | fem | fünf |
<カタロニア語の歴史>
ヨーロッパからイベリア半島に多くの文化や言語がもたらされる中で、8世紀から10世紀ぐらいにカタロニア語の言語領域が広がっていき、13世紀から14世紀にかけてかなり大きな言語領域をもつようになります。カタロニア文学は14世紀から15世紀にかけて最盛期を迎えます。しかし、16世紀から18世紀ぐらいにかけてカタロニア語が衰退していきます。これはなぜか。それまではフランスの方から様々な文化を取り入れて文化的にも成長していましたが、16世紀から18世紀にかけてスペインはマドリードを中心に南部のセビリャからどんどん世界に出て行くようになります。1492年にコロンブスがアメリカ大陸に到達したのを機に世界に対する植民地支配が始まっていったわけです。ですから、当時スペインの国というのは地中海貿易をもって栄えていたのですが、国の力が南に向くようになり、カタロニアが取り残されていったわけです。それにつれて言語も文化もだんだん衰退していったという状況があります。そこで今度は国が統一されてひとつになると、国の政治経済の中心がマドリードになり、当然バルセロナを中心としたカタロニアとの間でライバル意識が出てきます。それがどんどん進むに従って様々な言語の統制あるいは弾圧が行われていったわけです。そういう状況でやっと20世紀の頭にカタロニア語を復活しようという動きがあり、多くの研究所あるいは辞書ができるようになります。しかしながら、1936年から1939年の間にスペインの中で内戦があり、それによって1975年にフランコ総統が亡くなるまで再び徹底的な弾圧がなされます。カタロニア語が弾圧され、バスク語も弾圧され、またガリシア語も弾圧されます。スペイン国内においてスペイン語以外はだめだったわけです。今でもカタロニアに行きますと、スペイン語はエスパニョールと言うのですが、「エスパニョール」と言うと「ノー」と言います。なぜかというと、スペインの人にとってはエスパニョールでいいわけですが、カタロニアの人にとってはエスパニョールではなく、カステリャーノと言わなければいけません。すなわちカタロニアの人にとってみれば、カタロニア以外の地域の言語はカスティリア語で、カタロニアの言語はカタロニア語なわけです。それほど徹底的なライバル意識をもっていて、それがいまだに続いてきています。1980年に憲法が出され、スペインはスペイン語が公用語であり、カタロニア語が公用語であり、ガリシア語が公用語であり、バスク語が公用語であるとされ、ひとつの国の中に4つの公用語をもつようになります。バルセロナには300万に及ぶ人口があり、マドリードよりも経済力があると思われます。しかし、カタロニアはひとつの国として独立し得る人口をもっていながら、また経済力をもっていながら、そこにそのまま留まるというのはいったいどういうことだろうか、これはひとつのおもしろい問題だと思います。
<数・時間・曜日>
[数]
1:u,un,una(ウ ウン ウナ) 2:dos,dues(ドス ドゥアス) 3:tres(トゥレス) 4:quatre(クアトラ) 5:cinc(シンク) 6:sis(シス) 7:set(セット) 8:vuit(ブイット) 9:nou(ノウ) 10:deu(デウ) 11:onze(オンザ) 12:dotze(ドッザ) 13:tretze(トゥレッザ) 14:catorze(カトラザ) 15:quinze(キンザ) 16:setze(セッザ) 17:disset(ディセット) 18:divuit(ディブイット) 19:dinou(ディノウ) 20:vint(ビント) 21:vint-i-u/un/una(ビンティウ/ウン/ウナ) 22:vint-i-dos/dues(ビンティドス/ドウアス)/100:cent(セント) 101:cent u(セント ウ)/110:cent deu(セント デウ)/200:dos-cents(ドス センツ)/500:cinc-cents(シンク センツ)/1000:mil(ミル)/1000000:milió(ミリオ)
数は以上のように表します。17は10+7という言い方をします。この言い方が17から始まります。
[時間の表し方]
| 9:00 | Són les nou(del matí). (ソン ラス ノウ ダル マティ) | |
| 1:30 | Són dos quarts de dues(de la tarda). (ソン ドス クアルツ ダ ドゥアス ダ ラ タルダ) | |
| 3:37 | Són dos quarts i mig de quatre. (ソン ドス クアルツ イ ミッチ ダ クアトラ) | |
| 4:07 | Són mig quart de cinc. (ソン ミッチ クアルト ダ シンク) | |
| 6:22 | És un quart i mig de set. (エス ウン クアルト イ ミッチ ダ セット) | |
| 10:05 | Són les deu i cinc(de la nit). (ソン ラス デウ イ シンク ダ ラ ニット) | |
| 10:40 | Falten cinc minuts per tres quarts d'onze. (ファルタン シンク ミヌッツ ペル トゥレス クアルツ ドンザ) | |
| 10:40 | Són tres quarts menys cinc d'onze. (ソン トゥレス クアルツ メニス シンク ドンザ) | |
| 12:00 | Són les dotze. (ソン ラス ドッザ) |
いくつか例を挙げてありますが、表現の仕方が二通りあります。10時5分の言い方は“Són les deu i cinc(de la nit).”です。これは“deu”が「10」、“cinc”が「5」で、10時5分ということで、一般的にわかりやすいです。しかし、従来のカタロニア語の表現によれば、1時30分は“Són dos quarts de dues(de la tarda).”と言います。“quarts”は「4分の1」、“dos”は「2」ですから、“dos quarts”で「4分の1がふたつ」、“dues”は「2」です。1時30分をなぜか2時30分という言い方します。その下の3時37分は“Són dos quarts i mig de quatre.”と言います。“dos quarts”は「4分の1がふたつ」、それと“mig”は「半分」で、4分の1の半分です。“quatre”は「4」です。そうすると、3時37分に対して4時と30分と4分の1の半分という言い方になります。このように3時37分では4時という数が出てくる、1時30分では2時という数が出てきます。なぜでしょうか。これはややこしいことではありません。私達はどこに視点があるかということです。何時からスタートしたかではなく、何時に向かって何分進んだかという考え方です。1時30分の場合は2時に向かって30分進んだ、3時37分の場合は4時に向かって37分進んだということです。
[曜日]
それと関連したことで曜日をみていきますと、曜日は月曜日から“dilluns”(ディリュンズ)、“dimarts”(ディマルツ)、“dimecres”(ディメクラス)、“dijous”(ディジョウス)、“divendres”(ディベンドラス)、“dissabte”(ディサブタ)、“diumenge”(ディウメンジャ)と言います。一週間の始まりは日曜日なのか月曜日なのか。国によって考え方は違いますが、日本のカレンダーは基本的には一番左側に日曜日があります。カタロニア語やスペイン語のカレンダーは一番左側に月曜日がきています。どちらでもいいのです。ものの考え方がどこで始まるかということです。