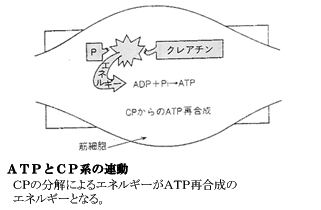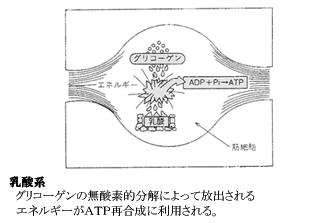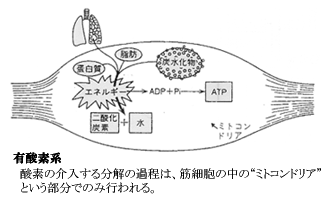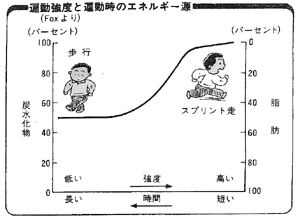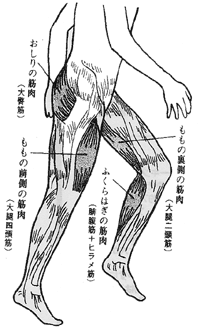「基礎代謝を高めるためには運動をする」。基礎代謝というのは、生命を維持するためにだけ使うエネルギーのことです。そして、この基礎代謝量が1日の消費カロリーの中で占める割合が非常に高いのです。運動をすることによってエネルギーが使われるだけではなく、基礎代謝も高まっていくという、2つの良いことがあります。運動は無理をせずに、ウォーキングやジョギングが良いのです。かつては、30分間続けて歩かないと効き目が無いと言われていたのですが、最近は10分単位の細切れで1日合計30分でも効果はあるそうです。
では、なぜウォーキングが良いのでしょうか。100メートルをダッシュすると、例えば世界記録を持っている人は9秒ちょっとで走ります。一方、普通の人が100メートルを歩くと1分近く、あるいはもっとかかるかもしれません。この2つは移動した距離は同じなので、物理的には使ったエネルギー、つまり移動エネルギーは同じと考えます。
ところが、人間の場合はそれぞれ使ったエネルギー源が違うのです。私達が体を動かす時に使う直接的なエネルギー源は、ATP(Adenosine Tri Phosphate)というものです。それを作り出して体を動かしています。100メートルダッシュをした時と普通に歩いた時とは、エネルギー源の使い方が違うのです。それは、ATPを作り出すのに脂肪を使うのか、あるいは糖質を使うのかということです。
一番上の
「ATPとCP系の連動」の図を見て下さい。これは、筋肉中に蓄えられているCP(クレアチンリン酸)が分解して出来るエネルギーを使って、ATPを作り出しています。100メートルダッシュをするような運動で最大限使うと、計算上は7.7秒分のストックしかないと言われています。そして、2番目に
「乳酸系」と書いてあります。これは筋肉中に含まれているグリコーゲン(糖質)を分解して、ATPを作り出しています。これも、100メートルダッシュをするような運動で最大限使うと、計算上は33秒分のストックしかありません。この2つは、酸素を使わなくても起きるエネルギーなので、アネロビック(無酸素性)な機構と言われています。それに対して、一番下の
「有酸素系」という図があります。上の2つだけではエネルギーは、すぐ無くなってしまいますので、どんなに長い時間運動をしても、運動を続けられるようなエネルギーの供給機構というものがあるのです。それを示したのが下の図です。これは、筋肉細胞にあるミトコンドリアで、脂肪やタンパク質が呼吸で取り入れられた酸素と反応して分解されて、ATPを作り出しています。これをエアロビック(有酸素性)な機構と言われています。20年ぐらい前から、エアロビック・エクササイズという運動が女性の間で流行っていますが、それはまさに、このようなエネルギーを生み出す機構を基にして考え出されたものです。
今、私がお話したことを分かりやすくまとめたものが、「運動強度と運動時のエネルギー源」という図です。歩行の場合、エネルギー源として炭水化物も脂肪も50%使うということを意味しており、スプリント走の場合、脂肪はほぼ0%で、炭水化物を100%使うということを意味しています。したがって、この図は、運動の強度が強いと長時間続けることはできないが、逆に、運動の強度が軽いと長時間続けることができるということを示しているのです。私達は生活習慣病を考えますと、特に脂肪を減らそうとします。脂肪を減らす運動の代表的なものが、歩行になるわけです。もちろん歩行だけではなくて、他にもいろいろあります。水泳もゆっくり泳げば、歩行よりも効果が高かったりします。特に膝や足首等に故障を抱えている方には、水泳が推奨されています。
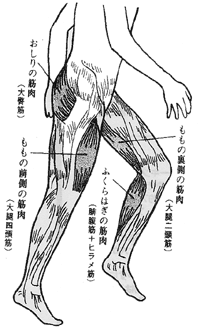 |
| 歩くときに使う筋肉 |
それから左の図を見て下さい。1歩を広げて歩くと、お尻の筋肉、いわゆる大臀筋(だいでんきん)を使います。この筋肉は、筋肉の量としては非常に多くあります。同じように歩くのでも、このお尻の筋肉まで使って1歩を歩けば、エネルギーもたくさん使うということです。これは欧米人に多く見られる歩き方です。昔から洋服スタイルだったので、こういう歩き方になったわけです。一方、日本人特有の歩き方というのは、膝から下だけしか動かさない歩き方です。膝から下だけというのは、着物の場合、非常に歩きやすいのです。これは良いとか悪いとかの問題ではないと思うのですが、同じ1歩を歩いてエネルギーの使い方が違うのであれば、やはり少し大股で歩き、お尻の筋肉も含めて他の部分も使って歩いた方が非常に良いと思います。