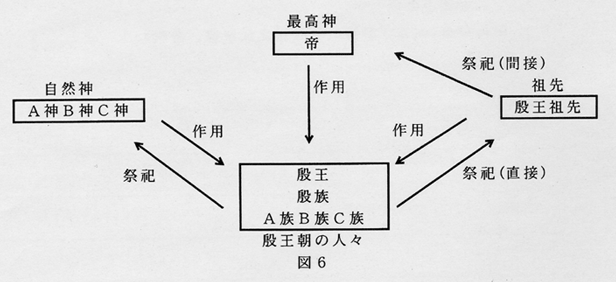もう一度第2段階をみますと、どうも構造が不自然に思われます。特に祖先と帝との関係がどうなっているのかがよくわかりません。自然神と帝との関係もよくわかりません。少なくとも祖先神が非常に重要になってくるのですが、この時代の祖先と帝がどういう関係にあったのかというのが知りたいところです。それがわかれば、第3段階、第4段階に構造が変化していく、祖先がだんだん重要になっていく、その変化がよくわかるのではないかと思います。
池澤優さんの1999年の論文におもしろいことが書いてあります。池澤さんによりますと、「卜辞には世代の近い祖先が遠い祖先に「賓」せられ、後者が更に帝に「賓」せられるという例がある。」ということです。それがたった一枚の亀甲の中に書かれています。その一枚を全部出すと煩雑ですので、省いて、おもしろそうなところだけをみます。
庚申の日に卜し、殻が貞う、翌乙巳の日に父乙(小乙)を祭るに羊を用いんか
貞う、咸(大乙)は帝に賓せられるか
貞う、大甲は咸(大乙)に賓せられるか
甲辰の日に卜し、殻が貞う、下乙(祖乙)は咸(大乙)に賓せられるか
貞う、下乙(祖乙)は帝に賓せられるか
貞う、大甲は帝に賓せられるか (以上、合1402による。一部省略)
実際に何か供物を捧げて祭っているのは「父乙」、自分のお父さんだけということです。
これにより、池澤さんは「○○は帝に賓せられるか」というのは、例えば父乙を祭り、祖先を祭り、しだいにその祖先から祖先に伝令のように祭った祈りの内容が伝えられていって、最終的には帝に賓せられる、賓せられるというのは迎え入れられるというように解釈しています。これは非常におもしろい祖先と帝との関係です。直接自分の祖先を祭ることによって間接的に祈りとか願いとかが帝に到達し、帝からいろいろな作用が起こってくると捉えられるのではないかということです。この「帝に賓せられるか」というのは、一つの亀甲史料しかありませんのでなんともいえません。それで、もしもそういった近い祖先を祭って最終的には帝にいろいろな内容が伝わるというように先ほどの亀甲の一枚を解釈していいものとしますと、第2段階、武丁時代の帝と祖先との関係はよほどはっきりし、図6のような構造になります。そのとおりかわかりませんが、殷王朝の人々が直接殷王の祖先を祭祀し、ここで留まって祖先からいろんな作用があったり、たたりがあったりする場合もありますが、場合によっては間接的に最高神の帝に伝わります。殷の祖先というのは帝と殷王朝の人々をつなぐ非常に重要なものになっていきます。帝と人間をつなぐ媒介です。中間の祖先というのは、地位があがっていくとほぼ帝と対等になっていくという構造の変化が起こりやすいし、わかりやすい、と考えられます。
今でもまだまだ甲骨文というのは出てきています。新しい史料が出てきていますので、そういったものをどのように殷の人々と祖先と帝と自然神の関係に反映していくか、おもしろいところだと思います。ただ「A(祖先)はB(帝)に賓せられるか」という解釈ですけれども、場合によっては、帝を祭る時に一緒に祖先のAも祭るのだという解釈もあります。そうすると全く逆になって、帝を祭っているのだということにもなってしまいます。古代文字の世界というのはそういったたったひとつのことでひっくり返ってしまうという部分もあり、断定してしまうのは怖いところでもあります。