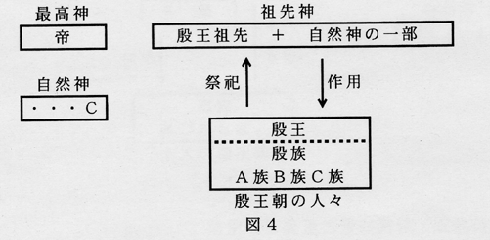第3段階の神と殷の人達との関係は図4のようになります。
(帝、自然神、殷王朝の人々との間の祭祀・作用の矢印は省略) |
最高神、自然神と殷族の関係は横に置いておき、まずみていただきたいのは祖先神がかなり重要になってきて、帝と並んでいる、相対的に帝の地位が落ちてきたということです。祖先神が殷の人達にとって非常に重要なものになってきたという構造の変化がみられます。また、殷の人達は祖先を祭り、そして作用を受けますが、どういうわけか、今まであった自然神の一部分を自分達の祖先の中に取り込んで、自分達の遠い昔の祖先として祭るようになってきたようです。そのあたりを具体的な書かれたものでみていきます。
<自然神>
自然神の祖先神化ということで、
これ高祖の*(自然神)に祝せんか。用いん、王は祐を受けん (合30398)
辛未の日に貞(と)う、禾(みのり)を高祖の河(自然神)に求めん、辛巳の日に祭らんか (合32028)
自然神に自分達の祖先だという「高祖」という称が付けられています。自分達の祖先の中にいくつかの自然神を取り込んでいき、それで相対的に祖先(神)の地位がどんどん重要になってくるわけです。
<祖先神>
さらに祖先神が帝に近づいていきます。
貞(と)う、それ帝甲(祖先)より祭り・・・ (合27437)
乙卯の日に卜す、それ帝丁(祖先)を祭り一羊を歳せんか (合27372)
「甲」あるいは「丁」というのは祖先のひとつですが、それに「帝」という修飾語が付けられています。祖先に「帝」という修飾語を付けておそらく帝に近づけているのでしょう。相対的に祖先の地位がぐんと高くなったということが考えられます。
もうひとつは、この時期に「受祐」、たすけを受けるという意味の言葉が使われています。これは特別な言葉で、第2段階の武丁のころは戦争開始時に「祐(たすけ)を受けんか」と最高神の帝に聞いたりしています。こういった最高神の帝からたすけを受けることはよく第2段階の武丁の時代にはありましたが、それ以外にはこの言葉は使われていません。しかし、第3段階になると、
王が、それ父庚(祖先)を祭るに、王は祐を受けんか (合563)
今まで最高神に使っていたこの「受祐」という言葉を祖先に使い始めています。これも祖先の地位がどんどん高くなってきた、あるいは重要になってきたということのようです。
もう一度第3段階をみますと、武丁時代とそれほど大きく変わっていませんが、相対的に祖先神の地位があがって、帝と同等なのかわかりませんが、盛んに祭祀をして作用を受けます。また自然神の一部を自分達の遠い祖先のひとつとして取り込んできたという第3段階の図ができてきます。