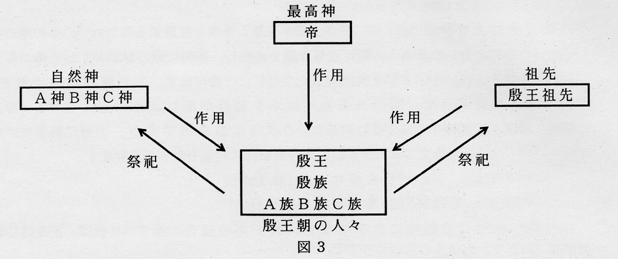武丁時代の甲骨文より、第2段階の神と殷の人達との関係は図3のようになります。
殷王朝の人々は祖先を祭って祖先からいろいろな作用を受け、自然神を祭って自然神からいろいろな作用を受けています。そういった働きかけを受けていると信じているわけです。しかし、最高神の帝を祭るということはなかったようで、一方的に作用だけを受けるという構造になっています。そのあたりのところを書かれたもので確認します。
<帝>
帝の働きというのは戦争や都市の建設などの人事に関わる部分があります。
丙辰の日にトし、殻(占い師)が貞(と)う、帝がこれこの邑(都市)を終しめんか (合14210)
帝は都市を終わらせることができるということです。
他に帝の働きには雨や日照りを支配し作物の実りを左右するという自然現象をつかさどる部分もあります。
丙子の日に卜し、殻(占い師)が貞(と)う、翌丁丑の日に帝がそれ雨ふることを命ずるか (合14153)
帝は雨を降らせることができるということです。
ここまでみましたように、帝は人事と自然現象に関わってきます。しかし、特に帝が祭られたとか供物を受けたというようなものは出てきません。
<自然神>
自然神の働きは農作物の実りや降雨など自然現象に関わってきます。
戊午の日に卜し、賓(占い師)が貞(と)う、祭りて年(みのり)を岳・河・*(自然神)に求めんか (合10076)
実りを「岳」・「河」・「*」(以下、適当な漢字がない場合、*や※という記号で代用します)といった自然神に求めるということです。また、この文より自然神は祭祀を受けていることがわかります。
ここからがわかりにくい話ですが、どうも自然神については自然神と同じ地名や族名があったようです。
己卯の日に卜し、出(占い師)が貞(と)う、今日、王それ河(地名)に往かんか (合23786)
「河」はおそらく地名で、自然神と同じ地名があるということです。
丁卯の日に、婦※(女性名)が二対を示せり。岳(卜骨の管理者。族名) (合13854)
「岳」は卜骨の管理者、おそらく族名だろうと考えられています。
自然神については地名に同じものがあり、族名にも同じものが出てくるということで、自然神のあるものは、もともとは殷王朝以外の諸族によって祭られていた神であり、征服過程で殷の祭祀に取り入れられたのではないかと考えられています。
その次におもしろい現象で、自然神に対して「帝とよばれる祭祀」(帝祭)が行われています。しかし、その内容はよくわかっていません。
・・・河(自然神)に帝せんか (合14531)
貞(と)う、王亥(自然神)に帝せんか (合14748)
伊藤さんは、自然神に対してこの「帝とよばれる祭祀」が行われていることから、もともとは帝の働きは自然神と同じようなものだったのでないか、つまり帝はもと殷の自然神であったのではないか、というようなことを言っています。確かに帝祭はいくつかの自然神に対して行われています。ただ調べてみますとそれだけではないようです。
癸未の日に、下乙(先王)に帝せんか (合22088)
三犬をもって黄爽(旧臣)に帝せんか (合3506)
祖先に対して帝祭を行ったり、古い家臣に対しても帝祭を行ったりしています。このような例をうまく処理しないと、帝祭を自然神に対して行っているから帝というのはもともと自然神のような存在だったということは、はっきり言えないかもしれないというところです。
<祖先神>
祖先神の働きは王をはじめ生人に対する「たたり」です。
乙亥の日に貞(と)う、大庚(祖先)がたたりせるか (合31981)
貞(と)う、歯を疾めり、父乙(祖先)に祭らんか (合13652)
祖先は生人に対してさまざまなたたりをします。それで祭ってなんとかしようということで盛んに祭っています。祖先神も自然神と同様に祭祀を受けているということです。
もう一度武丁の時代を確認します。最高神である帝は人事や自然現象について殷の人達にいろいろな作用をします。作用しますが、どうも祭ってはいません。殷の祖先はいろいろなたたりをするので、それに対して盛んに祭っています。自然神は主には自然現象の作用をし、それに対して祭祀をするというような構造になっているようです。自然神にはいろいろな神がありますが、それはそれぞれのA・B・C族を征服する過程で祭の対象として自然神の中にA族の神を自然神として祭る、B族の神を自然神として祭る、C族の神を自然神として祭るというようなことになっていて、殷族とA・B・C族の関係をよろしく保っているらしいのです。これが第2段階で、第1段階のA・B・C・D族の平面的な関係からこのような構造ができてくるということです。