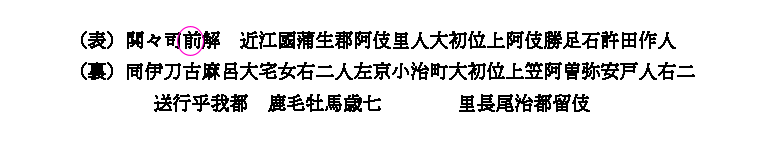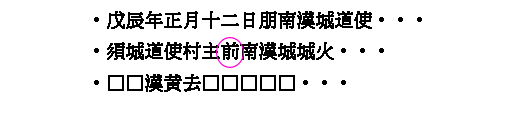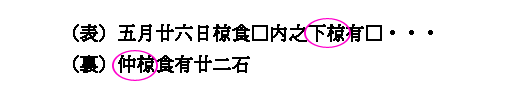朝鮮半島の用字法の影響が、他にどんなところに見られるかということをご紹介していきたいと思います。まずは、「
前」という字の使い方です。7世紀の日本の木簡を例にとって説明します。
この木簡は、「
尾治都留伎(おわりのつるぎ)」という名前の里長が、「2人の人が通るので、関所のお役人の方々はどうかよろしくお願いします」と出した通行許可証です。(表)の「
関々司前」をご覧下さい。これは尊称です。今の私達で言うと、例えば“侍史”と手紙に書く使い方なのです。こういう様式を「申前木簡(しんぜんもっかん)」と言います。宛名のところに「
前」という字を書いて敬称を表すことが7世紀にはかなり多いのですが、8世紀の日本では無くなってしまいます。なぜこれが無くなったかと言うと、「
前」という用法は朝鮮半島の文書行政の様式であり、中国直輸入の様式が普及するにつれて、中国ではそういうやり方はしないということが分かってやめたと説明できます。その証拠は、ソウルの東にある二聖山城という古いお城の跡から出てきた木簡から分かります(李成市氏の研究による)。
2行目の「
村主」の次に尊称の「
前」が使われています。「
道使」というのは、中央の政府から地方へ派遣されてきた役人で、「
村主」は、在地の豪族が中央の役人として任命された人です。内容は、「南漢城にいる「道使」という役人が、須城(恐らく、二聖山城のその当時の名前だったのだろうと推定されています)にいる「道使」と「村主」の2人に、のろしのことについて連絡をした」というものです。「村主」は「すぐり」と読みます。これは実は、上の日本の木簡に出てくる「勝」も「すぐり」と読みます。こういったところからも、日本と朝鮮半島の似ている点が分かります。
それから、前章で少し触れた「
椋」という字ですが、これを前章の木簡では「椋(くら)」と読んだように、「倉庫」の意味で日本の古代では使います。大宝律令の施行によって作られた大宝2年の『美濃国戸籍』にも、「椋人(くらひと)」のような名前が出てきます。しかし、この字は中国では「椋(むく)」という植物を表します。日本でも8世紀に入ると、この字を植物の「椋(むく)」で使った形跡がありますが、7世紀までは「倉」の意味でしか使いません。つまり、中国での用法を知らないのです。なぜこんなことがあるかというと、それも朝鮮半島との関係で説明がつきます。かつて、新羅の都であった韓国慶州から出た木簡(8世紀に入ってからのもの)に、「
下椋(しもつくら)」「
仲椋(なかつくら)」という語句が見られます。出てきた場所はガラス製品の工場の跡であり、そのガラス工場に勤めている職人さん達の給食の伝票で、5月26日の椋(くら)で食べる食事は・・・・という内容です。
さらに、中国の『周書』という歴史書には、百済には「内椋部(うちのくらぶ)」「外椋部(そとのくらぶ)」という役所があったということが書いてあります。高句麗では、倉のことを「桴京」と書き、これを当時の言語に復元してカタカナ発音すると、「フクラ」なのだそうです。これが元になって、木偏に「京」をつけて、朝鮮半島で「
椋」という合字を作ったのではないかという説があります。