次は、滋賀県西河原森ノ内遺跡から出土した680年頃の木簡をご紹介します。これは役人間の手紙です。
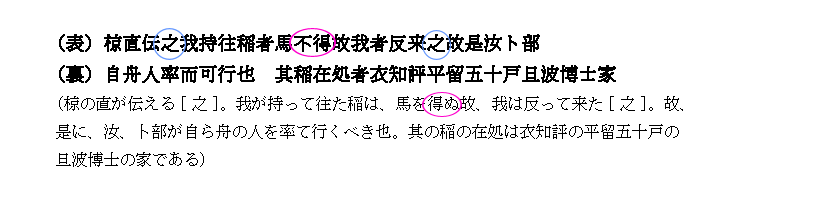 |
新羅の『壬申誓記石』と森ノ内遺跡の木簡は、全く同じ性格の文章とは言えませんが、朝鮮半島ですでに、自分の言語の順番に漢字を並べるという書き方が成立していたからこそ、7世紀の終わりの日本でも同じ書き方をすることができているわけです。このように、朝鮮半島では漢文を自分の言語に即して読み下し、さらには自分の言語に添って漢字を並べるということが行われており、6・7世紀の日本列島に文章の書き方が伝わった時には、恐らくこれがまず来たのだろうと思われるわけです。中国とは地理的に遠く、中国の律令での文章の書き方はもちろん勉強はされていたのですが、断続的に、しかも時代的には遅れてやって来るのです。
そこでこういう例えをしてみました。現在、私達はカタカナ語を大変よく使うようになっていますが、英語で読み書きする時には通じないものを多く使っています。例えば「インフラ」という言葉があります。これは「infrastructure」という英語で、「基礎構造」や「基盤」が本来の意味です。ところが日本語では、この「infrastructure」を「インフラ」と略すと同時に、意味が全然違っています。道路を整備したり、電気・ガス・水道を通したりすることが「インフラ」だということになってしまっています。つまり、カタカナ語にあたるのが朝鮮半島から学んだ漢文で、英単語にあたるのが正格の漢文です。恐らく7世紀まで、日本人が漢字の用法だと思って勉強していたのは、朝鮮半島の漢文だったわけです。それでひとまず、朝鮮半島風の律令にならった日本の行政制度ができてしまい、7世紀の木簡には、日本語風になまっている漢文で書かれているという現象として出てきます。しかしその後、天武天皇が中国直輸入の文化でなくてはいけないと、大変力を込めます。そのために遣唐使の派遣が何度も行われるようになり、本来の中国直輸入が取り入れられ、8世紀に入ると正格の漢文が書けるようになるのです。このあたりが今日の私のお話の中心になります。