日本の木簡は、数万点の規模で出ていて研究が進んでいますが、少し奇妙なことがあります。それは7世紀(飛鳥宮・藤原宮の時代)の木簡と、8世紀(平城京・奈良の都の時代)の木簡を比べてみると、8世紀の木簡の方が、正しい漢文に近い文体で書かれています。7世紀の木簡は、日本語風になまっているのです。これについては、遣唐使が7世紀の終わりから始まって、中国本土との交流が密になり、学力が上がって正しい漢文が書けるようになったのだろうと、こういう説明をすることもできます。しかし私は、朝鮮半島から学んだ形式から中国直輸入の形式へ切り替えが行われたという点を強調したいと思います。
朝鮮半島では古くから、漢文を自国語(高句麗語・百済語・新羅語)にあわせて改造した文体が発達していました。高句麗は、古代の朝鮮半島においては先進国で、早くから統一国家として成立していました。例えば、414年に建てられた『広開土王碑』は大変立派な漢文で書かれているそうです。ところが、『中原高句麗碑』と呼ばれる石碑は同じ5世紀前半のものであっても、漢字で文が書いてありながら、漢文としては読めない部分を持っています。これは恐らく、当時の高句麗語や新羅語になまっている漢文であり、この『中原高句麗碑』は、当時、高句麗が新羅の領土を次々と侵略する時代だったので、高句麗はこんなに権威があるということを新羅の人達に読ませたいという目的で書かれたと言われています。それから、新羅の石碑は6世紀以後のものが残っていますが、大体事情は同じです。例えば、一番古い503年の『迎日冷水新羅碑』には、新羅の王が冷水という土地(今でもあります)の近くにある村の財産に関する紛争を上手く治めたという話が書いてあります。これもなまっているそうです。しかし、百済についてはどういうわけか、残っている石碑は全部正しい漢文です。なまったものは残っていません。この理由ですが、どうも朝鮮三国(高句麗・新羅・百済)の中では、百済が中国文化の世襲に最も熱心だったようです。中国の文献にこんなことが書いてあります。「新羅の人と中国から来た人が話をしようと思うときは百済人が間に通訳に入る」。これを韓国の言語学者達は、他の2国に比べて、百済では中国語の水準が高かったのだろうと推量しています。
そして、なかには漢文として読もうと思うと、なまっているどころか全然読めないが、当時の新羅語なり高句麗語なり百済語を書いたのだと思えば読めるというものがいくつか残っています。一番極端だと言われるものを1つご紹介します。新羅の『壬申誓記石』です。石碑といっても小さな石に文を刻んだものです。
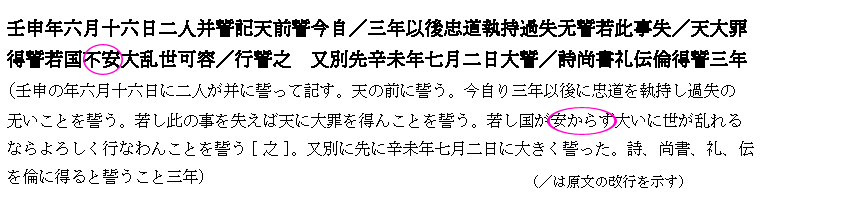 |
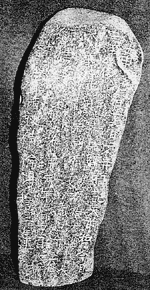 |
| 『壬申誓記石』 |