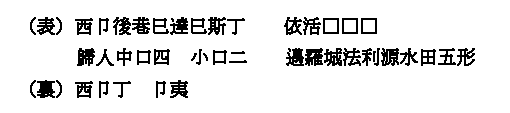それでは、日本列島に影響を強くもたらしたと思われる朝鮮半島の5・6世紀の状況は、どうだったのでしょうか。これは最近日本でも、それから大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国でも、大変研究が進んできている分野の1つです。その時に一番大事なのは、木簡など、土の中から出てくる資料です。これはどういう点で大事かというと、その当時のものがそのまま出てくるということです。『古事記』は8世紀の本だということになっていますが、『古事記』の一番古い写本は鎌倉時代です。つまり、その当時そのものではないのです。ところが、木簡などはその当時そのものです。日本では、すでに数万点の木簡が出ており、7世紀後半のものがここ10年の間、全国に出ています。従って、7世紀の後半には、律令制度の施行が全国的に行れていたということです。今、学者達が注目しているのは、7世紀の初め、さらには6世紀の木簡の出土です。しかし朝鮮半島の方では、木簡はあまり出てきていません。なぜなら、気候と植生が違うからです。朝鮮半島では、日本列島と違って石碑の類で、古くていいものがいくつか出ています。それから、朝鮮半島南部の茶戸里(たほり)遺跡から筆と小刀が出ていて、これが紀元前後のものだということが分かっています。筆と小刀があるということは、小刀を使って木簡を作っていたこと、そして筆があるということは、そこに漢字を書いていたことが分かるわけです。
 |
| 図3 |
そこで、大変大事だと言われているものを1つご紹介します(李鎔賢氏、李成市氏の研究による)。図3は、百済の扶余の宮殿の庭の跡から出たと言われる7世紀前半の木簡です。それを活字体に直したものが次のようになります。
「
西卩後巷(せいぶこうこう)」は○○市○○区○○町のような、○○区○○町にあたります。このように、行政区画を分けていたということがこの木簡で分かります。行政区画を分けていたということは、律令的な法律の施行をしていたという一種の証拠になります。それから「
巳達巳斯(いだついし)」は、人の名前です。今の韓国人や朝鮮人の名前とは違います。これはモンゴル等、漢民族ではない人たちの名前で、たぶん土着の名前だろうと思われます。そして、「
中口」は大人、「
小口」は少年のことです。この木簡は、「西卩後巷(せいぶこうこう)」という町の「巳達巳斯(いだついし)」という人の家来である男が、百済の民になった大人4人と少年2人を引率して「法利源」の水田へ耕しに行くための通行証だと言われています。こういったことから、朝鮮半島では遅くとも6世紀には中国の律令風のやり方をしていたということが確認されるわけです。