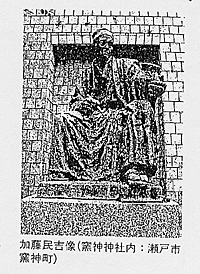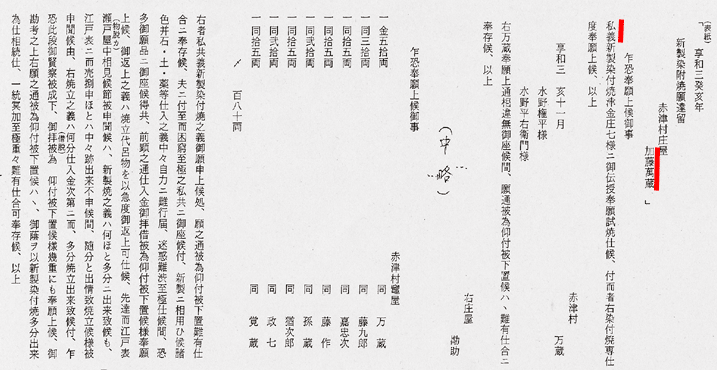瀬戸の窯業は、先程の蔵元制度の導入とほぼ時を同じくして染付焼が始まります。従来、磁器の生産が瀬戸の窯業界・産業界を救ったという形で、蔵元制度よりも染付焼を始めたことが産業化を一層推し進めたと言われていますが、私は、やはり蔵元制度がきちんとあったからこそ産業化が進んだと捉えています。
右の写真を見て下さい。瀬戸市の窯神町の窯神神社に、この像が立っています。瀬戸物祭りというのが今でも毎年9月に盛大に行われますが、この瀬戸物祭りの神様が「加藤民吉」です。磁器を始めた“磁祖”としての民吉を、瀬戸地域の恩人として高く評価しているわけです。この人物のおかげで瀬戸の窯業は発展したことに間違いないと思うのですが、私自身はちょっと違う観点を持っています。民吉が九州天草、そして佐世保で技術を磨いて瀬戸に戻ってきて、磁器生産が一気に進んだと言われていますが、実はそれ以前に瀬戸村では、先程の「加藤唐左衛門」が先頭に立って染付焼を作っていたのです。また、従来は瀬戸村だけでやっていたかのように言われていましたが、瀬戸市史の編さんの中で、赤津村でも積極的に行われていたということが分かりました。
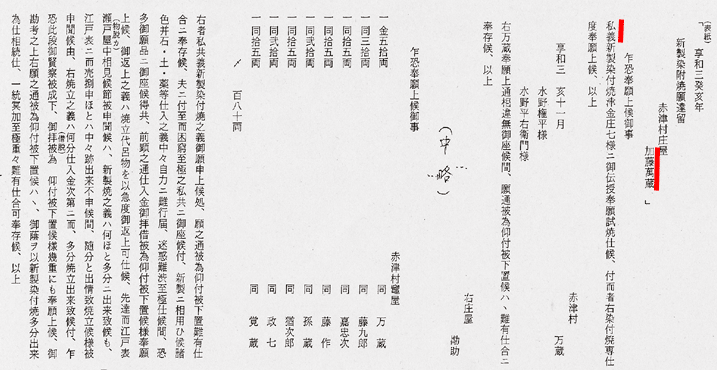 |
| 史料3 享和三年 赤津村庄屋による新製染付焼願達留 |
その赤津村の例が史料3になります。これは民吉が帰ってくる前の話です。その段階で染付焼が行われていたという事実があります。 “私義”とありますが、この私というのは赤津村庄屋の萬蔵さんです。尾張藩の勘定奉行の津金庄七という人物が染付焼を推進します。そして、今度は染付焼を専業にしたいという意欲を見せているのです。中略の後、尾張藩の勘定方にお金を貸してくれと拝借金の願いをしています。なぜ拝借金の願いを立てているかというと、竈屋営業を続けていく上で染付焼をきちんとやるためには、これだけ必要だというお願いを立てているのです。その中に非常に面白い部分があります。江戸で瀬戸物を扱っている問屋が、『江戸では染付焼を欲しがる者がたくさんいて、赤津村で染付焼をいくら焼いても江戸の需要には追いつかないからもっと精を出して焼いてくれ』と言っています。つまりこれは、染付焼は江戸ではものすごい評判になっているという意味なのです。従来は、染付焼は民吉が戻ってくるまでは駄目だったという話ですが、私は必ずしもそうではなくて、地道な尾張藩勘定方などの努力があって、瀬戸だけではなく赤津でもいろんな試し焼が進み、努力の果てに染付焼は本格的に展開したと見ています。