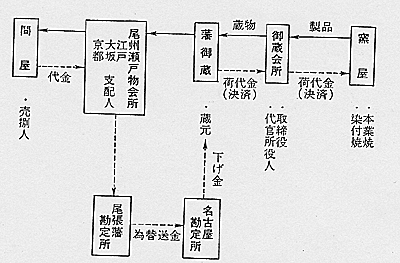私は蔵元制度が実は瀬戸窯業の発展、そして近代の産業に繋がっていく土台を作ったであろうと考えています。
蔵元制度はいわゆる国産、専売です。専売というのは役所が買い上げるというシステムです。よって、自由な販売はできないのですが、瀬戸の焼き物は尾張藩の産物という形で扱われるわけです。その制度以前の流通は、竈屋の株仲間の間でしか統制していない非常に緩やかな管理で商品を流していましたが、これ以降ずいぶん変わってきます。
蔵元制度導入のきっかけは、次のとおりです。竈屋が品物を納めて問屋から代金を貰おうとしても、問屋が支払ってくれないという状況が江戸時代中期ぐらいから続いていたといわれています。これは、“不さばき”ではなくて、“代金の踏倒し”だと瀬戸の関係者はいうわけです。それをどう改善するかということで蔵元制度が生み出されたのです。というのは、品物が尾張藩のものということになると、代金の踏倒しは不可能になります。踏倒すということは尾張藩に対して楯突くという事になるので、代金の回収がスムーズになるという仕組みなのです。さらに、尾張藩としては税金がきちんと入るようになります。藩財政にとってもこれは条件として非常に良く、間に入る商人にとってもスムーズに物が流れるということで、生産者・間に入る商人・藩の三者が合意して一気に導入されたといわれています。ちなみに、この蔵元制度を導入したのは瀬戸の陶器取締役の「加藤唐左衛門」という人物の提案だという話です。
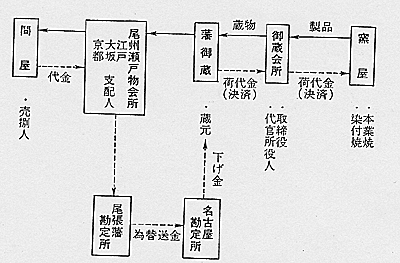 |
| 図2 尾張藩の陶磁器専売制度 |
実際の製品とお金の流れが図2になります。
まず竈屋がいて、製品を御蔵会所に出します。そして、御蔵会所から尾張藩の御蔵にまわって、そこから江戸や大坂、京都の瀬戸物会所、要するに「支配人」のところにいきます。その後、「売捌人(うりさばきにん)」、いわゆる問屋が買い入れて、全国の小売りにまわっていくという形で全国展開するということです。そして、問屋から代金が入って、それが瀬戸物会所に戻り、尾張藩の勘定所へいきます。この尾張藩の勘定所は、江戸、大坂、京都にあります。そちらにも藩の屋敷を持っているので、そういったところに付随して勘定所なるものが置かれ、そこから今度は名古屋の勘定所に為替送金されます。そして今度は尾張藩の御蔵へいき、御蔵会所を通じて竈屋の方に代金が最終的に戻ってくるという形で物・お金が流れるわけです。これは見ていただくと分かるように繁雑です。竈屋が焼き物を納めてから代金が納入されるまで3ヶ月かかるので、竈屋にとっては苦しいところです。原料や燃料等を購入する資金繰りに困ってしまうのです。もちろん生活費にも困るので、代金が納入されないうちによく前借をします。蔵元がお金を貸し付けて、竈屋に営業させて代金で返済させるという竈屋と蔵元の関係だったということです。ある意味では蔵元に統制されているという状況がみえるわけですが、しかし製品自体はきちんと販売できるという形で進みます。なお、竈屋達の営業を保証して統制も加える、そういう存在が竈屋取締役です。簡単にいうと、一般の村での庄屋です。まさにこの竈屋取締役は、お上に対して納品するのと同時に、竈屋の生活を成り立たせるという責任を持って竈行政をとり行っていたのです。