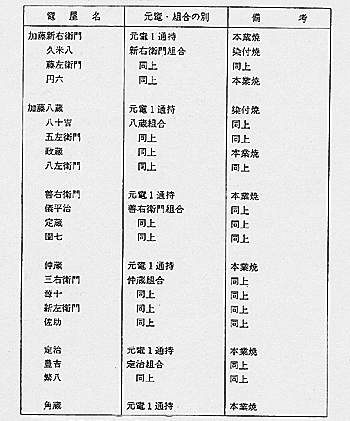竈屋集団は、竈を持っている「元竈株保持者」と、その元竈を持っている人と組み合って組合として竈を焼いている「焼き株保持者の集団」という形で一つの単位ができています。
表1は、「下品野村竈屋組合構成表」という表です。一番上を見て下さい。かつて竈大将と呼ばれた大変有力な竈屋の「加藤新右衛門」のところが「元竈1通持」となっています。竈は1通(とおし)という単位で呼びます。組合に入っているのが「久米八」、「藤左衛門」、「円六」の3人です。この4人で1つの竈組合を構成していたということなのです。それ以下このような形で元竈が6つあって、組合としても6つと考えていいのですが、「角蔵」だけはちょっと例外です。大体は3人〜5人ぐらいのグループで組合を構成しています。そこでは、元竈を持っている人がいて、更に連房式の登り窯で焼く焼き株を持っている人達がいて、それぞれの房ごとに自分の焼き物を詰めて焼いたのだろうと思われます。なお、竈屋の組合は、「元竈株保持者」が権力を持っていたのではなく、平等な関係だったといわれています。
【窯業不況とその後の竈屋の増加】
| 表2 尾張国瀬戸村窯数・窯屋(陶工)数変遷 |
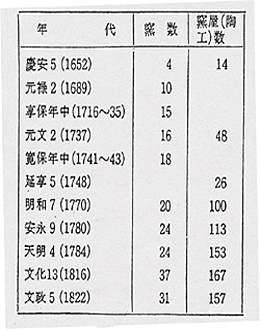 |
順風満帆というか、そういう形で瀬戸窯業が発展していくかに見えたのですが、しかしそうは甘くはありません。瀬戸窯業のライバルは九州地方にも当然ありますし、それ以外にもいくつか窯業の産地がでてきたりします。そういう状況で、17世紀の後半に焼き物が余るという現象が起きます。いわゆる窯業不況といわれる時代です。
その後の竈屋は順調とはいえませんが、増加していきます。表2は瀬戸村の竈屋の変遷で、これは窯数と陶工数がどう変わったかという表です。見ていただくと分かる通り、データとして明確でないところがありますが、途中までそれほど窯数は増えていないということなのです。1750年ぐらいまでの間は、窯業がそんなに大きく飛躍したという感じはなく、むしろその前の段階は不況で、一時期竈屋をやめているようなところもあったということです。その後窯数は少しづつ増えて、陶工数は延享5年(1748)から明和7年(1770)の間にはかなり増えています。また、天明4年(1784)から文化13年(1816)の間で窯数は急激に増えますが、理由は染付焼です。いわゆる磁器生産が本格的になったということです。これは瀬戸村だけではなくて他の村でも状況は同じで、その頃に陶工数は伸びています。
【尾張藩の保護策】
このような不況もあった中で、なんとか凌いでこられた背景には尾張藩の保護策があります。尾張藩は竈屋保護策をかなり手厚くやりました。竈屋は原料等に費用がかかるためにお上からお金を借りるのですが、当時の、江戸時代の初期の一般的な利子は年利30%です。しかし、このお上から借りた拝借金は12%又は15%ぐらいです。従って、かなり低利の融通的な形で拝借できるということで、竈屋にとっては補助になります。それから尾張藩は京都等から竈屋営業に似たようなものが入ってくると、それを追い出すということをやります。さらに瀬戸の窯業関係者以外が何か似たようなことをやりだすと、それも禁止するという形で瀬戸の窯業者を保護する営業独占も行われます。これはいわゆる株仲間と考えてもいい形態になっているわけです。