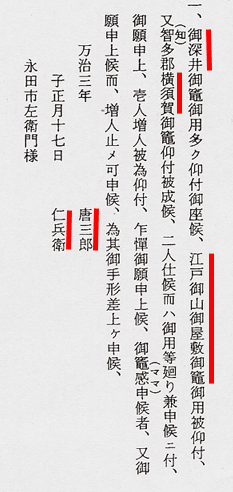右の史料2「御竈屋一人増員願」ですが、1660年(万治3年)に「唐三郎」と「仁兵衛」という人が尾張藩の国奉行「永田市左衛門」に、御竈屋を1人増やしてほしいという願いを出します。“御深井(おふけ)”というのは、名古屋城の御深井丸です。そこに瀬戸の「御竈屋」の竈が築かれていて、御用としてそこでいろんな焼き物を焼くのですが、それ以外に江戸の尾張藩邸にも竈が築かれていて、竈屋達は江戸まで出向きます。さらに、知多郡の横須賀(現在の東海市)に尾張藩主が横須賀御殿を作ります。江戸時代、海水浴のことを“潮湯治”と呼んでいましたが、そういう海水浴用の御殿を作って、そこにも竈が築かれるということなのです。先程の竈師の系図にもありましたが、「唐三郎」と「仁兵衛」という兄弟の家だけが御竈屋御用をしていたのですが、忙しすぎるということで1人増やしてくれと、この願書が出るのです。「御竈屋」というのは普通の竈屋ではありません。お上の御用を仰せ付けられ武士の格式を持っている竈屋で、藩主との目見えが許されるという竈屋です。
【新しい技術・・・大窯から連房式登り窯へ】
近世的な発展を考える場合には、やはり技術的な問題を考える必要があります。
次の図を見て下さい。左が窖窯(あながま)、真ん中が大窯、右が登窯、いわゆる連房式登り窯というものです。
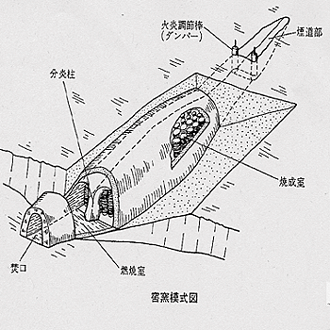 |
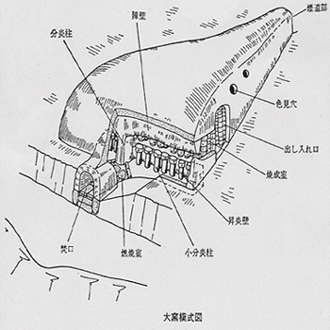 |
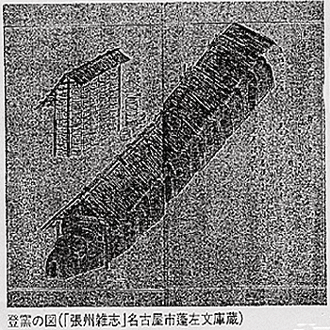 |
それに対して大窯は、中世末から江戸時代の初めにかけて、非常に多く見られる窯です。これは半分だけ地下に入っている窯、半地上式の窯で、焼成室と燃焼室は別になっていて、燃焼室の方から火をまんべんなく入れていくための分炎柱というものも改良されてきているということが分かります。それから焼成室の中も覗けます。半分地上に出ているので、出し入れ口もかなり改良が進んでいます。
やがて近世的な窯となるのが登窯です。これは完全な地上式になります。“連房”といって、傾斜のあるところに下から段々に房(ふさ)を連ねるような形で窯を築いていくものです。これは房というそれぞれ個別の空間が特徴的です。大窯の段階では、竈屋集団には有力な竈屋が1軒あって、そこに従属してみんなで一緒に焼くという形だったと考えられています。それに対して連房式というのは、竈屋が房をそれぞれ利用する小経営の形に展開してきたということを示しているのではないかということなのです。ちなみにこの窯は、九州のほうから伝わったという話です。冒頭でもお話しましたように、やはり九州のほうから技術を入れてこないと太刀打ちできない状況であったことは間違いないのです。そういう形で新しい技術が導入され、竈屋集団に大経営から小経営という形の自立の方向が見えてきたということです。