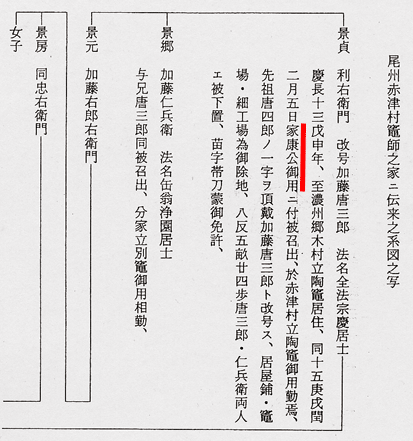 |
| 史料1 「赤津村竈師系図」 |
それとは逆に、1610年あたりに竈屋達が美濃地方から戻ってくる「竈屋呼び戻し」という現象が起きます。
史料1「赤津村竈師系図」を見て下さい。これは「景貞 利右衛門(かげさだ りえもん)」という人物が名前を改めて「加藤唐三郎」になるのですが、土岐市の曽木のあたりに移住して竈を立てていたのが、それが慶長15年(1610)に瀬戸の赤津村に戻ってくるという話です。「竈屋呼び戻し」の古い考え方は、尾張藩の初代藩主「徳川義直」が呼び戻したと言われているのですが、「義直」はまだこの時10歳ぐらいの子どもであり、瀬戸物の名人を美濃の国から呼び戻したいと言うだろうか、と非常に疑問だったわけです。
しかし史料1から分かるように、これは間違いなく家康公が御用だということで召し出し、竈を立てたということなのです。尾張藩の初期の国奉行、これは同時に家康の奉行人でもあるのですが、この人達が実はその書付をだしているわけです。従って、呼び戻した主体は家康とその奉行人であるというのが正しいのだろうということです。
ちょうどこの時、名古屋城が建築途上で、大都市名古屋が作られようとしていました。もともと尾張藩の中心は名古屋ではなく清洲にありました。そして、家康の四男の「松平忠吉」という人物が清洲にやって来ます。しかし、彼は若くして亡くなり、家康の九男義直が入ってくるのです。尾張は幕府の軍事的拠点となる地域でしたが、清洲では西日本を攻めるための要となる城を築くには弱い点があったので名古屋城が築かれ、それに従って尾張藩の中心が南下します。1610年代〜20年代初頭まで、お城と名古屋という巨大都市が建設される時期が続きますが、実は竈屋達はその時期に戻ってくるのです。そういう巨大な都市に焼き物を供給するためには、ある程度便利なところで大量に作って持っていく必要性があるので、名古屋城が築かれるのに合わせて戻ってきたと考えるのが妥当ではないかと思うわけです。今までは悲しい出来事、それから尾張藩主の哀れみという形で「竈屋呼び戻し」を見ていたわけですが、決してそういうものではなく、経済的、政治的なことが貫徹して、出て行ったり呼び戻されたりしているのだということです。