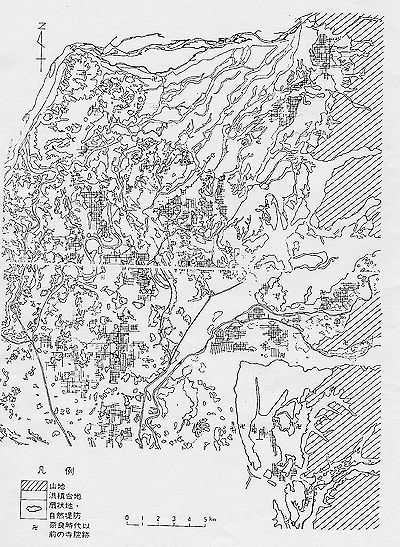 |
| 図5 金田章裕による尾張平野の条里地割分布 |
まずこの図では条里の里のマスメがどれぐらい現実に広いのかということを洗い出したわけですが、非常に精密に調査をしてみますと『濃尾平野一帯、尾張平野一帯に完全に存在したとはとても言えないものではなかった』というのがこの図の結論になります。一番左下のあたり、正方位とずれる斜めになった条里がちょうど富田荘の部分ですが、こういう斜めにずれてしまった条里がその他各地に存在し、かつ、それぞれの条里には微妙につながらない面も残っていたわけです。現実に条里というのは、あまりよく残っていないものだったわけですが水野説の考え方でいきますと、本来、奈良時代に完全に条里は引かれたのだけれども、後の時代に「班田収授」がなくなり、さらに、洪水によって川の流れが変わりやすい場所だったため、条里というのは消えていったのではないかと最初は思われたわけです。
ところがこの地図をよく見ていきますと、ななめの線で取り囲まれたところが洪積台地、ないし扇状地にあたる場所になります。条里がよく残っているところは、洪水を受けなかった洪積台地ではなく、その逆なのです。沖積平野のほうに比較的よく残っているのです。そこから考えると、洪水によって条里がかき消されていったという考え方はあまり当てはまらず、水田を作るのに向いた沖積平野から条里は作られていたということになります。全体として条里を作るという計画があったとしても、現実の景観においてはより部分的に作られていたことが、尾張国の条里の特徴だと分かってきたわけです。
そうなると、奈良時代の歴史遺産だと思われていた条里は、違う性格を併せ持っているものだと、考えを修正していく必要がでてきました。今のところ、一番一般的な考え方を紹介しますと、条里とは『時代によって性格を変えながら受け継がれてきた』というものになります。簡単に三段階に分けると、まずは奈良時代「律令の条里」。「班田収授制」と一応結びついていたであろう時期の条里です。
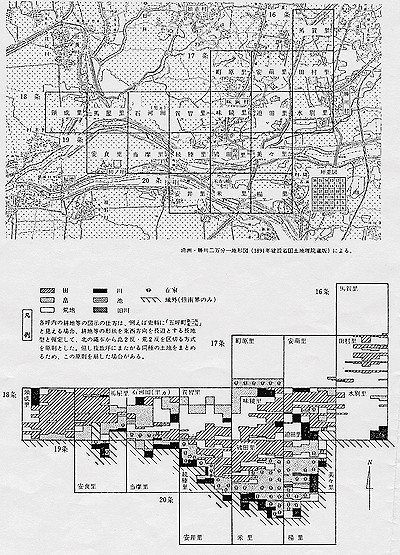 |
| 図6 安食荘の条里と康治2年(1143)の土地利用 |
そして、土地の私有が広まっていくにつれて「荘園」が増えていくのですが、それぞれの「荘園」ごとで条里を用いた土地管理が行われるようになってきたというわけです。その1つの例が、富田荘で暫定的に3×4=12の里があるわけですけれども、これは国に迫られて作ったというものでもなくて、奈良時代に作ったものが奇跡的に残っていたというわけでもなくて、実質的に中世に入ってから条里の持つ土地管理という特徴、そのすぐれた特質のみを受け継いだ条里ということになります。これを「荘園の条里」と呼んでいます。他にも若干例があり、庄内川と矢田川が合流するあたりに、安食荘(あじきのしょう)という「荘園」があるのですが、この「荘園」も「荘園の条里」を利用しています。これは完全に、この「荘園」独自に作られたのか、その前からあったものなのか、若干なりとも継承しているのかはやや微妙であります。 しかし、「荘園の条里」の記録が残っていると、当時の土地利用の風景が復元できるということになります。それが図の6です。、これは安食荘の中の田と畑と荒地の分布を大体のところで示したものです。ただこの安食荘の条里の並べ方については、いろんな説があり、この説が絶対という訳ではないのですが、代表的な説ということで引用いたしました。この条里のシステムというのは、古代や中世の農村の風景、土地利用のあり方を知りたい、研究したいと思う者にとっても非常にありがたい存在であります。当時の一表示システムのおかげで非常に細かいレベルでどこに田があり、畑がありということが、当時の土地台帳を通じて現在にも甦るというわけです。