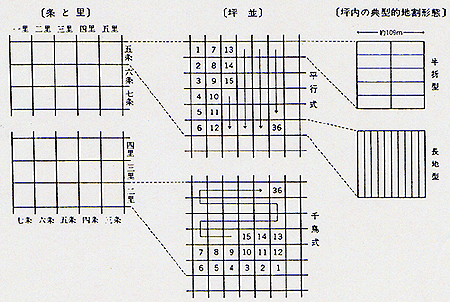 |
| 図2 条里における土地表示の仕組み |
このように、建前上はある土地の場所を示すために、○○の国、○○郡、○○条、○○里、第○○ノ坪という言い方をすると、日本の中である土地が存在している場所を示すことが可能になるわけです。つまり、『土地を表示しつつ管理する』というシステムが条里の第2の特色になります。従って、この○○ノ坪とか○○条という地名が残っているのも、やはり条里の名残ということになります。
普通、三条や四条というと、京都とか奈良のように都があったところに付くものだと思うわけですが、そういう都が全然ない地方にも○○条という地名が残っていたり、あるいは郡によっては北の条とか、東の条、南の条ということで、北条とか南条という言い方をするケースもあります。そういう地名が残っている場合は条里の名残ということになります。
次に条里の第3の特色ですが、今挙げた2つの特色に基づいて、土地の管理と配分・配給を行う、つまり、「班田収授制」と呼ばれていたものがこの条里の目的だったのではないかと、とりあえずは考えられています。ここでちょっと引っかかるような言い方をしたのは、実はこの条里が何のために作られたのかということは、確実な証拠としてはよく分かっていないのです。「班田収授」を行ったということは、古代国家の公式な記録に残っていて、大化の改新から902年頃までは行っていたという建前になっています。その公式な記録の中に、「班田収授」を行うので条里を作れという命令が明確な形では一切存在しないのです。しかも「班田収授」に遡って作られたと思われる条里も一部には見つかっていて、この条里の本当の目的、最初の出発点が何であったのかということは意外にもよく分かっていないのです。一応、古代の、特に奈良時代頃の律令国家が「班田収授」に利用したものである、だからこそ、これだけ大掛かりな工事を行ったり、土地の名前をつけたりするという国家的な事業を行ったのだろうと想像されてきたわけです。