 今までお話ししてきたことは、一応私の専門ですが、特に研究を自分なりに今、日常的にやっているのは、これからお話しする融通と土地所有という問題であります。この土地というのは、重要な担保として活躍します。これは、今でも一緒です。土地がないと、銀行からお金が借りられないということがあります。土地は、担保として活躍するということなのですが、その所有の仕方、ムラ共同体が、その所有にどう関わっていたのかということが大変重要な問題になります。そこで、これからお話していく土地所有論とか土地制度史というものですが、これは今、先細りの歴史学の中でも、さらに人気がないものなのです。しかし、土地所有論というものに対しては、実は、追い風も吹いております。そこで、追い風の1と追い風の2というのを挙げたいと思います。
今までお話ししてきたことは、一応私の専門ですが、特に研究を自分なりに今、日常的にやっているのは、これからお話しする融通と土地所有という問題であります。この土地というのは、重要な担保として活躍します。これは、今でも一緒です。土地がないと、銀行からお金が借りられないということがあります。土地は、担保として活躍するということなのですが、その所有の仕方、ムラ共同体が、その所有にどう関わっていたのかということが大変重要な問題になります。そこで、これからお話していく土地所有論とか土地制度史というものですが、これは今、先細りの歴史学の中でも、さらに人気がないものなのです。しかし、土地所有論というものに対しては、実は、追い風も吹いております。そこで、追い風の1と追い風の2というのを挙げたいと思います。追い風の1は、先ほどからお話しているムラ共同体、ムラ社会の再評価という問題です。“村悪玉論”から徐々に解放されてきています。“悪玉論”というのは、要するに、封建社会の遺制として残った、古い制度としての村、共同体というものを、徹底的に壊さなくてはいけないということ、これが戦後の日本社会で、“悪玉論”を考えた人たちの合言葉だったわけです。今、ムラ社会、共同体を悪玉と考えるような議論はないかも知れませんが、かつてはありました。そこから、解放されてきているというところがあります。そして、共同組織論とかいう形で、共同体そのものというよりは、ムラとムラが結びつく組合、共同組織というところで、もう少し広げて考えていくというスタンスが取られてきているということです。これが、土地所有についても非常に追い風になっております。それと、共同体が土地に対してどう関わっていたかということを、みんなで少しずつ考えるようになってきましたので、 一つの追い風であるだろうという気がします。
追い風の2は、社団国家論というのが、今から20年ぐらい前に非常に流行しました。これは、外国史、特に、フランス史の研究者たちから、社団と言って、当時、耳にたこができるぐらい聞きました。私もあまり詳しいことは解かりませんが、私なりの考えで述べますと、様々な集団とかを媒介にして、いわゆる、国家権力と民衆の間をつないで考えるというものだと思います。そして、そこの民衆と集団、集団と国家というものとのやりとりで、いろんな政策決定とかがされるというようなもので、いわゆる、単純に、国家の側が民衆を直接支配するというものではなくて、間に社会集団というものを置いて、国家支配をとらえるという理論だったように思います。集団を媒体とした関係論というのはそういうことなのですが、そういう中で、集団的土地所有論というのが生まれてくるわけです。江戸時代の百姓は、自分で土地を持っていました。ですから、一つ一つの土地は、いわゆる太閤検地以来、名請けするということで百姓が土地を持つわけですが、その所有自体が、完全に個人的な、あるいは、家の所有というものではなくて、実は、ムラ社会、村共同体、あるいは、村の中の百姓が集団的にそれに何らかの形で関与する、管理するというようなものとして捉えられないかという議論が起こってきたのです。
そういう二つの追い風というものがあって、それを、いわゆる、金融論に導入して考えたということなのです。江戸時代は、非常に進んだ経済段階です。30年以上前の話では、封建社会は、自然経済だというようなことが言われていました。それは、全くの嘘だとだいぶ以前からなっています。封建社会は、かなり進んだ交換経済です。室町時代以前から、いわゆる為替がでてきます。今ある為替と同じです。至る所で為替が使えるわけではありませんが、ある都市と都市の間では、為替が使われているというようなことが、もう室町以前にあるわけです。これは、日本社会の一つの経済段階なのです。そして、そのような進んだ経済段階で、お金の問題を研究することは、大変重要であると私は常々考えていました。そこで、江戸時代の金融というものを具体的に考えた場合には、実は、年貢未進というものを基本とした、年貢未進を契機とした金融というものになります。未進というのは、年貢が払えない状態です。年貢未払いのことを、年貢未進といいますが、これを契機とした金融が、ムラ社会では行なわれるわけです。一方で、お金を借りた場合に、返せない事がよくあります。返せない時には、土地を担保にしておきますので、土地が取り上げられてしまうという状況があります。又、お金を借りる時に、今度は、その土地を何とか取り戻したいという土地取戻しへの活用もあるのですが、よく考えますと、江戸時代の金融というのは、だいたい年貢未進ということから出発していっているという動かせない事実があります。そして、こういう金融は、今の社会で言うと、みんな消費者金融なのです。要するに、お金がとにかくなくなって、それで補填していくというような消費者金融的なものになっています。だから、積極的な産業への投資とかといったところでの金融というのは、ある意味では非常に少ないという特徴があると思います。農村金融の基本は、年貢立替です。もちろん投資型というのは、非常に少数ですが、全くないわけではありません。商品生産地帯というのは、全国にいくつかあります。愛知県というか尾張の国の場合には、綿織物関係のマニュファクチャーが江戸時代の後期には出現しますので、そういったものへの投資という形での金融があったと思うのですが、そういった地域というのは、日本全国で言えばそんなに多くないわけです。ですから、江戸時代の金融を考えた場合には、年貢立替というものを軸に考えざるを得ないということです。もちろん、都市部は、話は別であります。
その次は、村での農間渡世についてです。これは、ノウカン、あるいは、ノウマと読んでいいと思いますが、農業の合間にいろんな仕事をしていまして、いわゆる、副業をしていました。それによってお金を稼ぐという行為も、村社会ではかなり行なわれたのですが、それで借金をある程度返せたとしても、農業生産を軸にした経営の建て直しというものがなければ、やっぱり、農村というのは、豊かにならないといいますか、進んでいかないわけです。ですから、炭焼とか、綿(わた)打ちとかといった農間渡世でお金を稼ぐ人は結構いますが、それでは発展はありません。やっぱり、農業生産を軸にした経営の建て直しというものが、どうしても重要であるということです。そこで考えたのが、百姓を守るシステムは存在しなかったのかどうかということです。従来の考え方として、江戸時代の村では、農民というのは分解してしまうものという農民層分解論という考え方がありました。要するに、農民階層というのは、基本的に持てるものと持たざるもの、つまり、土地をどんどん集積するものと土地を失っていくものとに両極分解していくということです。一方でブルジョア的に成長するものと、もう一方では、プロレタリアート的にといいますか、半プロレタリア、半プロとよく言うのですが、そういう形で分解していきます。両極分解を遂げるという理解がずっとありました。これは、基本線としては間違っていないと思いますが、しかし、そういう農民層分解論に対しては、少し疑問を持っています。資本主義への過程で、共同体というものの解体や農村、農民の分解というものは、絶対条件だったのかということが疑問なのです。両極分解というものを、歴史の必然として見るだけで良いのか。農民たちの生命と財産を守る努力というのは、どれだけあったのか。要するに、百姓を守り育てるシステムの話なのですが、この努力というものをもっと考える必要があるのではないかということです。そこで、農民層分解というものを阻止する動きを加えた上での農民層の新たな分解論を再構築する必要性があるのではないかということ、これが随分前に私が提起したことです。
そこで、具体的な話になりますが、融通=循環の分解論というものを提起しました。これは、要するに、地主と小作の関係です。土地を手放した小作と土地を集めた地主との関係をもう少しきちんと定義する必要があるのではないかということです。地主というのは、高利貸しで、土地をただ集めていて、小作をただ支配的にといいますか、小作をやらせるものとして捉えていいのかということです。そして、質地地主小作関係の中では、非常に融通としての側面が強いというように一応答えを出しました。これは、いわゆる利率、利子の問題です。これが、当時、どれくらいの利子だったのかと計算をすると、決して高率ではありません。収奪というようなことではなくて、むしろ、融通してやっているというぐらいのレベルです。それから、融通財の土地、要するに、土地が担保として動きますが、それを融通財というように理解しますが、融通財の土地は、一方的に地主の側にただ集積されるわけではありません。地主から請け戻されて、循環する場合が多いです。あるいは、土地が、別の地主のもとにさらに移動するということがあるわけです。そういう形で、実は、最初に土地を渡した小作と土地との関係は、継続していきます。土地を循環させることによって、元々の土地の持ち主の土地に対する関係というものは切られないという議論をしたのです。結局、これは、百姓というものを潰さないで村の中に残し、在村させるということに結果していくのです。そして、村の外に土地が出て行くのを防ぐ行為であったということなのです。
先ほどの話につながりますが、村役人が、質地による年貢立替をします。この場合の利子は、だいたい10%ぐらいだというふうに算出しました。そして、この当時の幕府が決めた公定利率があります。これは、だいたい15%で、幕末になると12% になるのですが、それがだいたいお上の決めた年利率です。そういったものよりは、ずいぶん低いのです。質地小作関係でお金を貸すという行為のほうが、幕府とかが決めた公定利率よりも低いのです。そういうことで、これは、融通というふうに考えざるを得ないと思います。年利10% というのは、今で言えば高利貸しです。しかし、江戸時代の初めは50%でした。それが、やがて30%になり、中期に20%になったのです。この20%は、普通の民間の利子で、当たり前の世界です。そこで10%ですから、やっぱり、これは融通です。そのように考えた方がいいのではないかということです。そこで、村役人=豪農というものを歴史的にどう位置づけるかということですが、これは、単に悪玉として考えるのではなく、融通の主体のような形で位置づける見方というのが、必要になってくるのではないかということです。
さて、百姓が、土地を媒介に分解阻止に動きます。土地は、共同体のシステム、ムラ共同体の一つのシステムの中で動いているという理解であります。「ムラの土地はムラのもの」という言葉が、よくムラ社会の中で語られているのですが、こういうムラの土地といっても、これは、ムラが持っているいわゆる共有地としての原とか山とかそういう入会地だけなのだろうかという話しです。「ムラの土地はムラのもの」という言葉は、実は、そういう共有地には限らないで、百姓それぞれが持っている耕地、自分の所持地にも関わっているのではないかということなのです。個別所持の耕地にも、ムラ共同体、集団の関与があるということです。
そこで、土地の売買、質入ということで、二つの例を示したいと思います。一つ目は、遠州見取村(現袋井市)の久蔵という人物がいて、この人が、お金がなくて年貢が払えないという時に、自分の親族にお金を借りようとしましたが、貸せる人はいませんでした。それで、結局、そういう自分の親類ではない人に、人というよりも、地域としての集落、小集落のまとまりを惣土人衆(ソウトニンシュウ)というらしいのですが、そういった所に全部委任してしまいます。自分の家族とか親族では、年貢が賄えないからそうするのです。そして、その地域単位の方に融通というものを任していくということなのです。やがて、そちらの方に、どんどん土地が任されるということになっていきます。
それから、二つ目は、幕末ですが、遠州高部村(現袋井市)の彦太夫という人物が、やっぱり年貢が払えないということで、村(行政上の村)に土地を差し出してしまいます。差し出しと言うのは、村のほうにお任せしますということで、自分の財産を出してしまうということです。ですから、今で言えば、税金が払えないので物納するということと同じなのですが、それで、その村の方に管理を任せてしまいます。そうすると、村の方は、今度は、喜助という人を探して、「あなた、この彦太夫さんが出したものを受けとってくれ。」と彼に言いました。受け取ってというのは、受け取った上でお金を出せということなのです。喜助さんが、年貢を代わって払えということです。そして、喜助と彦太夫の間には、地主小作関係ができるわけですが、そういう形で、村を媒介として、ムラ共同体がその地主小作関係を作るのです。お金を出してくれる人を村が探してやって、土地を差し出した人とそれを受け取った人の間での地主小作関係を設定してやるという形で、村が土地に関わっていくというような関係です。土地の売買とか質入に関わって、そのムラ共同体とか集団というものが、非常に強く関与する事があるということです。これは、自分勝手にはできません。そして、共同体の間接的な形でのその所有というのは、村を構成する百姓集団が、集団として所有を主張するということです。これは、渡辺尚志さん、神谷智さんという研究者がいるのですが、その人たちが、ムラ共同体が所有するということについて説明をしています。村が、間接的な形でそれぞれの百姓の耕地についても関わって、間接的な所有をしているという説明です。これは、おそらく、百姓集団というものが、集団として所有というものを主張することなのだろうと思いますので、集団的土地所有という形で私は言い換えていいと思っています。
そして、土地は、ムラ共同体だけではなくて、いろんなレベルで集団が関わってきます。具体的には、地縁集団、同族集団、それから、ちょっと大きなイエの構造といいますか、そういう中で、土地に対して関与をしていくという事があるのだろうということです。こういう形で江戸時代は、だいたい村が中心なのですが、村が土地に関わることによって、共同体を残して、悲劇的な分解を阻止したということです。融通=循環という行為がなされていくということなのですが、それは、集団的な土地所有というものを背景としてなされていくということです。
次に融通=循環というものは、地域社会の中で組織化されるということで、信用組合制度をちょっと考えてみました。そこで、だいたいドイツの信用組合制度というものは、日本に直輸入されたというようにずっと考えられてきたのですが、本当にそうなのかということを以前考えたことがあります。実は、融通=循環ということが、日本のムラ社会で組織化されて、もうすでに江戸時代には、信用組合の萌芽というのもあるという結論に私は達しました。これは、二宮金次郎ですが、彼が行なった報徳金融というもの、あるいは、その前提となった幕府の村備金融、あるいは、大原幽学の先祖株組合とかいろいろあるのですが、そういったものが、非常に信用組合的なものとして位置づけられるということなのです。
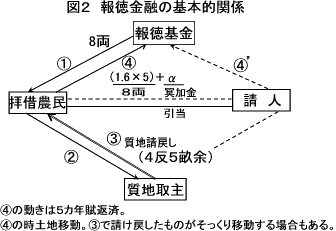
図2は、報徳金融の基本的関係というものです。お金を借りる拝借農民というものがいるのですが、だいたい報徳金融というのは、人手に渡っていた土地を取り戻すために、お金を借りる、それを、どのように返すかというシステムです。これを図式化したものが図2です。これは、今で言うと年賦です。月賦とか年賦とかありますが、当時、あまり一般的ではなかった年賦でお金を返していくというもので、しかも、無利子で当面返すということをして、最後の年だけ冥加金というものを返します。結局、これが利子になるのですが、毎年毎年返すものは、利子をつけていません。最後の一年分だけは、冥加金ということで、余得といいますかそういうものを差し出すというやり方をとるということなのです。つまり報徳基金からの低利融通をうけるシステムだったのです。
図3は、村備金融の体系と公金貸付の図です。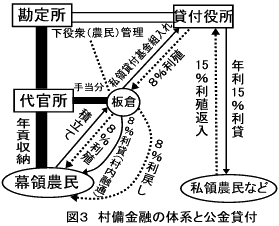
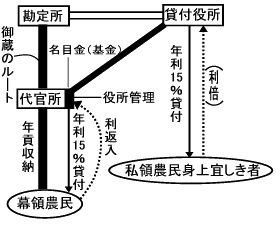 図3の左の方は、江戸時代の初めの頃から行なわれていた公金貸付です。江戸の馬喰町というところにお金を貸し付ける役所がありました。勘定奉行の支配下の役所ですが、そこがもともとやっていた貸し付けで、だいたいこれは、年利15%です。幕府公定の金利で貸し付けるというやり方をとっているわけです。ところが、図3の右の方の村備金融になりますと、農民が積み立てるお金が出てきます。さらに、年貢から2割分ぐらいが差し引かれて、手当分という形で、代官所なんかに設置された蔵があるのですが、そこに米穀がプールされるのです。手当分、それから、積立金というのがそこに資金として集まって、これが利殖されていきます。これは、幕領以外のお金を欲しがる人たちに貸し付けて、そこで利殖して、その差額といいますか、これがこの貸付役所の儲けにもなるのです。同時に、幕領農民の貯金も利殖して膨らんでいきます。もちろん、自分でそれを借りることもできます。自分たちで積み立てたお金なので、今度は、8%の利子で借りることができるということで、これも低利融通です。そういう形でこれは、やっぱり信用組合的であると思いますが、こういう形の金融方式ができたということです。
図3の左の方は、江戸時代の初めの頃から行なわれていた公金貸付です。江戸の馬喰町というところにお金を貸し付ける役所がありました。勘定奉行の支配下の役所ですが、そこがもともとやっていた貸し付けで、だいたいこれは、年利15%です。幕府公定の金利で貸し付けるというやり方をとっているわけです。ところが、図3の右の方の村備金融になりますと、農民が積み立てるお金が出てきます。さらに、年貢から2割分ぐらいが差し引かれて、手当分という形で、代官所なんかに設置された蔵があるのですが、そこに米穀がプールされるのです。手当分、それから、積立金というのがそこに資金として集まって、これが利殖されていきます。これは、幕領以外のお金を欲しがる人たちに貸し付けて、そこで利殖して、その差額といいますか、これがこの貸付役所の儲けにもなるのです。同時に、幕領農民の貯金も利殖して膨らんでいきます。もちろん、自分でそれを借りることもできます。自分たちで積み立てたお金なので、今度は、8%の利子で借りることができるということで、これも低利融通です。そういう形でこれは、やっぱり信用組合的であると思いますが、こういう形の金融方式ができたということです。
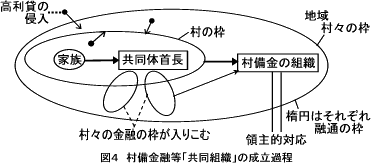 そして、図4は、村備金融などの様々な金融というものが、村社会の中に入ってきていることを図で説明したものです。ある家族が、お金が必要だということで、村の中で、共同体の首長、要するに、これは村役人なのですが、名主とか庄屋にお金を借ります。それが村の枠ですけれども、そこで結局、お金の都合がつかないということになると、これは、その次のレベルの村備金融とかそういったものの枠組みのほうに進んでいきます。全体としては、地域村々の枠があります。様々な金融というのが食い込んでいるという形で、金融的世界があったということなのです。こういった報徳金融、村備金融などの経験によって、日本社会は、欧米直輸入の近代化とか、産業化に対応可能だったということなのです。向こうの制度だけを直輸入すれば、おそらく、日本は、負けてしまう可能性もあったと思うのですが、そういう制度というものをほぼ備えていたから伍していけたということです。
そして、図4は、村備金融などの様々な金融というものが、村社会の中に入ってきていることを図で説明したものです。ある家族が、お金が必要だということで、村の中で、共同体の首長、要するに、これは村役人なのですが、名主とか庄屋にお金を借ります。それが村の枠ですけれども、そこで結局、お金の都合がつかないということになると、これは、その次のレベルの村備金融とかそういったものの枠組みのほうに進んでいきます。全体としては、地域村々の枠があります。様々な金融というのが食い込んでいるという形で、金融的世界があったということなのです。こういった報徳金融、村備金融などの経験によって、日本社会は、欧米直輸入の近代化とか、産業化に対応可能だったということなのです。向こうの制度だけを直輸入すれば、おそらく、日本は、負けてしまう可能性もあったと思うのですが、そういう制度というものをほぼ備えていたから伍していけたということです。