 「個が集団に埋没し主張が曖昧なムラ社会」と、よく言われます。村の構成員というのは、集団というものに属していて、何もいえない。そして、集団のボスというのがいる。あるいは、それをまとめているお上がいて、そのお上の上には、いわゆる、公儀、公儀公権、さらに言うと、戦前までは、いわゆる天皇的なものというか、天皇制的なものというのがその上にかぶさっていて、これは、絶対的なものでした。こういったものが集団を統括し、それに皆従順であったといった形で理解されてきているわけですが、政治的にといいますか、強圧的にという意味で、従順にされていた部分はもちろんあるのですが、しかし、江戸時代というのは、村社会が、本当にそのようにただ従順なものだったのかということをもう少し考えてみたいのです。
「個が集団に埋没し主張が曖昧なムラ社会」と、よく言われます。村の構成員というのは、集団というものに属していて、何もいえない。そして、集団のボスというのがいる。あるいは、それをまとめているお上がいて、そのお上の上には、いわゆる、公儀、公儀公権、さらに言うと、戦前までは、いわゆる天皇的なものというか、天皇制的なものというのがその上にかぶさっていて、これは、絶対的なものでした。こういったものが集団を統括し、それに皆従順であったといった形で理解されてきているわけですが、政治的にといいますか、強圧的にという意味で、従順にされていた部分はもちろんあるのですが、しかし、江戸時代というのは、村社会が、本当にそのようにただ従順なものだったのかということをもう少し考えてみたいのです。寄合ということについて申し上げていきます。百姓が、村の中で寄合う行為をします。ここで、会議をします。総会みたいなものですが、村の最終的な意思決定機関となります。これは、全員参加型が基本でありまして、そこでの決定は基本的には、全員一致です。要するに、そこで、意思統一をするのです。これは、一人でも何か違う考え方を述べますと、それを取り上げて延々と議論します。強行採決というのはしません。諄々と説得するとかというような形でやります。私がある資料で見た限りでは、3日、4日ぐらいずっと一つの事を議論しているというのがあります。その間、ご飯を食べに家に帰って、もう一度、寄合の会場であるお寺に戻ってくるというようなことは、いくらでもあったのです。村は、そのようにきちっと考えを詰めていくということをやっていました。これは、大変民主的な手続きで、全員一致というのが民主的かどうかは、ちょっとおいておきますが、少なくとも、誰かが、強引に何かを決めるというものではないという感じがします。寄合での取り決めというのは、集団は当然遵守します。百姓たちは、その村で決めたことは、村の法律“村法”と言ったりしますが、“村法”みたいなものも作ります。それを遵守して、組織化されて、集団行動を行います。ですから、集団行動というのは、最初から、集団的に全部訓練されていたというわけでもなく、寄合って決めたのだからやるんだという形で進みます。ただ、そういう寄合で、みんなで決めたことをやっていくということが、相当に日本社会が近代化するにあたっては、いい訓練になったと私は考えております。そういう意味で、近代化の準備ということが言えるのだろうと思います。
それから、郷例というものについてですが、これは、いわゆる、成文法といいますか、文字できちっと文章になっているようなものではなく、慣例みたいなものです。そして、村の寄合で決められた議定というのは、さっきの“村法”、村の法律と同じですけれども、そういうものを村議定と言います。村として、そういう法を作るのです。それを在地法と言います。在地社会の法というように言いますが、こういうものが、それぞれの村社会にあります。それぞれの村社会が、お上の法とは違うレベルの法をもっているということです。そして、その法には、罰則規定もあります。村八分とか言われるものがありますが、これは、火事と葬式については助けるけれども、後は何も面倒をみない、付き合いをしないというように通例いわれています。そういう村八分というようなものも、ある意味では村法なのです。村法に基づいてなされるわけであります。
こういう村の自立的な側面ということは、中世にもう少しさかのぼります。私は、江戸時代が専門ですが、もう少しさかのぼって、戦国時代までの村というのを考えていきます。これは、いわゆる、自検断権というものが、戦国時代までの村にはあったということなのです。自検断権というのは何かというと、自分で、犯人とかを処罰して、場合によっては、殺してしまうものです。中世の村、戦国時代の村というのは、盗みに入った人間というものを村人が見かけて、それを捕まえる。江戸時代は、相手が反抗してきたりして、仕方なく打ち負かして、殺してしまうということはあったのですが、殺してもいいということはないのです。江戸時代は、それをやってはいけないのです。要するに、そういう権限は、村にはないのです。しかし、中世の村というのは、自検断権が存在していて、自分で検断する権限があるということで、これは、認められているのです。ですから、盗人は打ち殺してしまえという在地の決まりというものがあったりするのです。こういう戦国時代までの村というのは、ある意味で、弱肉強食の時代であり、自検断権というものを持っていたのですが、近世の村になりますと、自検断権を放棄していきます。弱肉強食時代からの脱皮ということになるのです。
結局、多くの研究者といいましても、全員が全員でありませんが、戦国時代を一つの分岐点というよりも、大きな区切り目にして日本社会を二分法で見る見方が出されています。著名なところで、朝尾直弘さんという京都大学の名誉教授がいらっしゃいますが、この方は、「やはり、戦国時代が重要じゃないか。その統一後、日本社会というのが大いに変化し、現代につながってくる。」というようなことを言われて、それに反論する人は、あまりいませんので、だいたい定着しているのかなという気はします。今、述べたようなことで、中世・戦国時代というのは、かなり自立的な社会だったということです。村社会なんかも、相当に自分で全部処理できるような世界でした。
戦国時代までは、農民と武士というのが区別できない社会です。そういう中で、武力というものを村は当然持っているのですが、江戸時代になると、村は、刀狩りとかそういうものがあって、自律性というのが失われていきます。そこで、二分法というのがでてくるわけですが、問題は、これで村社会が、ただ単に従順になったのであろうかということなのです。私は、村は、刀狩でただ従順になったわけではなく、依存的で、他律的な存在でもないと思っていますが、要するに、こういうことが言われているわけです。村社会というのは、何か強い者がでてこないと、リーダーシップとかそういうものをとる者がいないと、非常に依存的で、集団の中に身を任している。ムラは、刀狩の後、非常に弱い社会になってしまったという見方があるので、そのように、日本社会が揶揄されたりするわけです。しかし、それは,本当にそうなのかなという気がするわけです。そこで言えるのは、殺し合う社会を止揚し、より公共的な存在に統治を委ねたという、こういう観点が大切だろうと思います。要するに、戦国時代は、奪い合い、戦って殺しあうという社会です。これは、決していい社会であるとは言えません。そこで、それをとにかくやめようというように考えるわけです。結局、刀狩で武力が取られてしまいますが、これは、権力の側にそれを渡して、自分から渡したとは思いませんが、とにかく、渡してしまったのです。それは、依存するということになるのですが、とにかく、平和状況というものを勝ち取ろうとしていたということだったのではないかと思うのです。今までの見方は、ただ強引に上からやられて、押しつぶされていたかのように思われていたけれども、必ずしもそうではないという見方が必要ではないかということです。
江戸時代には、いわゆる、公儀といいますか、幕府とか、そういう公共的な存在に統治を委ねるということと同時に、兵農分離ということが進んでいきます。先ほどお話しました村の中では、武士、農民というのは、未分離でしたが、それを、徐々に分離させて、支配者である武士は、都市に住むようにします。都市に住む支配者(行政責任者)です。今の考え方で言うと、国家公務員の役人になるのです。そして、一方、村の在方で住む者たちというのは、支配される側というように変わるのですが、支配されるといっても、平和状況の中で、自分のイエというものを中心に繁栄していこうというような形でシフトしていくのです。戦国時代を何とか終えて、村の中で、豊かというか、安定した暮らしというか、家(イエ)の永続というのを願うという方向に進みます。これは、小農民といいますが、それまで支配されていた隷属的な農民が自立して、自分の家(イエ)というのを確立していくという過程ともつながっていきます。そして、そういう小さな百姓たちが、村の中心になっていくという時代にこれから変わっていくのですが、そういう流れで、江戸時代というのを理解していくべきであると思うのです。
そこで、例えば、アメリカ型の銃を持ち、自分で身を守る社会と日本型の武器を放棄した社会との対比ですが、アメリカは、西部開拓で、みんな銃を持って戦って、勝ち取ったという武力と自立の社会であり、それに対して、日本は、刀狩されてしまって、他律的で弱い、強くない社会だと言われます。このようなことで、強い側からすると、日本というのは、どうしようもないというように見えるのですが、本当にそれはそうなんだろうかということなのです。自己の強さとその自律性を超歴史的に強調するのは、もはや時代遅れであるというように私は考えています。自己の強さと自律性というのは、要するに、軍事的な強さです。いわゆる、軍事力というのをやたらと強調して、戦争を仕掛けるというような形で自分の強さをアピールするというのは、ちょっと危なっかしいと思います。もし、そういうものが、国家としてのグローバルスタンダードになったら、大変危険なことではないかという気がしています。自律性一般を否定するわけではありませんが、それを過度に強調すると戦いしかなくなってしまうので、これは問題であると思っています。
ここで、寄合と村議定の方に話を戻しますが、この村議定というものは、村の中で寄合をして、一つの法律みたいなものを決めていくという営みですが、これは、一つの村社会というものに留まりません。村社会というものは、広がっていきます。村社会というのは、閉鎖的だという解釈が非常に多いのですが、これは、全然違います。村と村というのは、いろいろ連合を組みます。組合村などというように言います。これは、村と村が組み合わさるから、組合村というのですが、農業用水関係、飲料水などのいろんな水の問題で、村と村が組み合わさったり、山とか原の利用とかで、村と村が組み合うことは、無数にあるわけです。そして、そういう組合村の中にも寄合があるのです。村の中でしか寄合がないということではなくて、組合村を作っても、そこに、村の代表といいますか、そういう人たちが集まって、組合の議定をするわけです。村議定、それから、組合議定といいますか、そういうものをするわけです。
さらに、今度は、組合からその上のレベルにまで進んでいきます。どんどん広がっていきます。いわゆる、現代の選挙制度である代議制というものがありますが、それに近いような形で、自分たちの代表というものを選んでいって、代表に委任していくようになります。村からの代表を送り、組合議定を決めてもらいます。さらに、そこから、今度は、もうちょっと広い郡中議定というようにいうのですが、郡の中の議定というようになります。これは、何十ヶ村、何百ヶ村という村々が集まって、村が集まるというよりは、その村々の代表が数十人集まって、それこそみんな地域代表みたいな、議員さんみたいな感じで出てくるのですが、そういう人たちが寄り合うようになります。そして、また議定します。地域の法を決めるのです。ですから、村社会には、議会制度ではありませんが、類似したようなものが江戸時代の後期にはあります。そういう形で、村社会というのが広がっていったということです。
そして、頼み証文の誕生についてですが、これは、代表を委任する時に、この人に自分たちの代表としてそこに出て行ってもらって、いろんな働きをしてもらいたい時にこの頼み証文を書きます。代表という言い方は、当時しませんが、いわゆる、惣代と呼ばれる人を出す場合なんかにこの頼み証文を書きます。代表委任の仕方として、一つの例があります。これは、岐阜県の郡上で、有名な宝暦の郡上一揆というものがありました。その郡上一揆の時に、代表を送るという話ですが、惣百姓、つまり百姓がみんな出て行くということはできないので、いわゆる、代表といいますか,そういうものを頼んで送って、それで籠訴をしました。この籠訴の意味は、偉い人が籠で移動しますが、その籠を止めて訴状を届けるというのが籠訴というものです。この籠訴によって、惣百姓の存念といいますか、思いを遂げることができたという話です。これは、頼み証文の典型ではないのですが、頼み証文の一つのパターンをとっているものです。こういうことで、その代表というものを委任していくというやり方があるわけです。
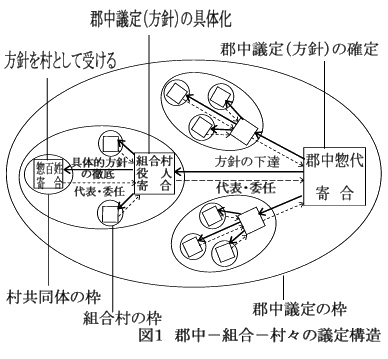 それから、この村議定、組合村議定、郡中議定という流れについては、図1で示しています。大きな楕円、卵形のところが、郡中議定の枠です。何十、あるいは、何百ヶ村の村の枠組みです。そして、その中に、やや小さな卵形が3つありますが、これが、組合村議定の世界です。さらに、その中に円があります。これが、村議定の世界です。こういう組み立てになっているわけです。惣百姓寄合があって、そして、代表委任して、組合村役人寄合があって、それが、組合村の枠組みでありまして、そこから今度は、代表委任して、郡中惣代の寄合があって、そして、全体として郡中議定を行ないます。そして、これは、各レベルで方針がそれぞれ決定されて下におろされていく、つまりより具体化されていき、方針化が進むということです。
それから、この村議定、組合村議定、郡中議定という流れについては、図1で示しています。大きな楕円、卵形のところが、郡中議定の枠です。何十、あるいは、何百ヶ村の村の枠組みです。そして、その中に、やや小さな卵形が3つありますが、これが、組合村議定の世界です。さらに、その中に円があります。これが、村議定の世界です。こういう組み立てになっているわけです。惣百姓寄合があって、そして、代表委任して、組合村役人寄合があって、それが、組合村の枠組みでありまして、そこから今度は、代表委任して、郡中惣代の寄合があって、そして、全体として郡中議定を行ないます。そして、これは、各レベルで方針がそれぞれ決定されて下におろされていく、つまりより具体化されていき、方針化が進むということです。
この方針の決定という過程は、完璧に自立しているわけではありません。江戸時代の社会で、すべて自立しているというのもちょっとありえないのです。こういう寄合とかというものは、主には、幕府からの御触れとか、そういうものが出された時に、それをどのように処理するかというようなことで、こういう議会といいますか、議定というのが設けられるのです。ですから、全部が全部、下からいろんな意見とか発想があって、下からのベクトルで出てきたものが上で政策化されて、下に下りていくという仕組みばかりではなくて、上で決めたものを、下で具体化させるというような、上からくるものも非常に多かったのです。そういう、上からのベクトルも非常に強いのですが、こういう形で、郡中、組合、村というものが、議定構造としてひとつの地域を構成していたと考えていいわけです。そういう形で、村議定から、組合村議定、郡中議定、さらには、国訴(こくそ)、あるいは、国訴(くにそ)と言ったりしますが、国規模で訴訟が行なわれたりします。これは、大坂とか奈良とかあちらの方面で、国訴というものが行なわれました。そういったところでも、代表委任が行なわれているということです。代議制の形成というものがなされるということなのです。
以上のように、村社会は、決して閉鎖的な社会ではないと考えてよいのです。領主支配というものを下から支え、行政というものを代行するというものだったと見ていいと思います。そして、日常性と組織性を持ったものとしての村社会の活動というものを、非常に重視したいと考えています。実は、あんまりこういう村議定だとかそういったものは、民衆の世界を語る場合に、そんなに重視されていませんでした。どちらかというと、世直しだとか、打ちこわしだとか、そういった何かちょっと派手な百姓一揆だとかそういったものの方が、民衆運動としては、大きな評価を得ていたのですが、やっぱり、少し違うのではないかと思います。そういう非日常的なものではなくて、今、お話した議定とかの、日常的なものから見ていく方がむしろ大切だと思います。そういったものから民衆の力量といいますか、そういうものを評価した方がいいのではないかと思っています。