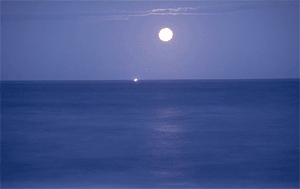 |
反歌
香具山と耳成山と
海神の
14番は13番とほぼ同じことを繰り返しています。香具山と耳成山とが闘ったときに、印南国原がこれを見に来たと歌っています。ここにでてくるのは、山とか土地です。これらが神として争ったり動いたりしている。その神の時代を歌っているようです。この歌がどこで詠まれたかは、いくつか議論があります。今考えられていることは、歌っているのは印南国原を通ったときのことで、この神話を中大兄(後の天智。多分、額田王たちも一緒に船に乗っていたのでしょう。)が詠みました。そのような歌い方をすることによって、その土地の神の心を鎮めようとしたらしいといわれています。
この当時の航海技術や、船の設備はとても乏しく、船旅はとても危険でしたが、陸旅も条件が悪かったのです。そのような歌が万葉集にたくさん出てきます。特にこの時代の人たちは、信仰と関わっていて、多くの人たちは、自分の生まれた土地を生涯離れなかったようです。その村の神様が自分達を守るという信仰上の理由で、その村にいることが一番安全で、違う土地へ行くことを非常に嫌いました。船旅にしても陸旅にしても往き倒れになった人の歌は、万葉集にいくつも出てきます。そのような物理的な恐ろしさが信仰に結びついて、自分のところにいる間は、自分のところの神が私を守る。それに対して知らない土地へ行くと知らないところの神はよそ者がくることを嫌って害を与えるという考え方を当時の人々はもっていたようです。
天智の故郷は大和ですから、印南国原という違う土地を通るため、その土地に対して、あなたのところにはこのような昔話、神話があり、それを私は思い出していますと歌っているらしい。このような歌い方によって、その土地の神は心が和められたのではないかと私たちは推察しています。それがこの歌の印南国原という場所で歌われた理由なのでしょう。
そのように考えると、15番の歌が何故一続きに出てくるのかよくわかります。海の神のなびかせている旗のような雲。これは吹流しのような旗です。ここに入り日が差していて、今宵の月夜はとても美しいだろう。夜の船旅で、月夜が美しいことは、海が荒れないことです。だから入り日がとても美しいのは、今夜とてもよい月夜になるだろう。船旅が安全だろう。このような思いを込めているようです。その点では8番の歌と同じような背景があったのでしょう。そして、15番の歌が13、14番の歌の内容に結びついてきます。この土地を安全に通れる、月夜も良い、だから神は私たちを祝福してこんなに良い月夜にしてくださったという歌い方らしいのです。このようによその土地に入ることを非常に怖がる状態でも、あえて西のほうに船を出しています。どうしても行かなければいけなかったのは、文明が欲しかった、高度技術が欲しかった、そのためには百済との結びつきをどうしても保っておきたかったという理由だったようです。
このような動機の中で斉明も船を率いて西へ行き、その子どもである天智(中大兄)もまた西へ向かっています。天武の妻である額田王もまた西へ向かっています。朝鮮半島の3つの王国のあり方や唐との関わり方という背景のなかで、「熟田津に船乗りせむと」と「海神の豊旗雲に入日さし」という歌が詠まれたと考えられます。