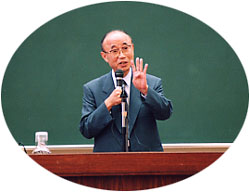第1行目「夕焼け小焼けで日が暮れて」。
今申し上げましたけれども、夕焼けを見ると我々は心騒ぎがする。じっとしていられない。こういう経験をして参りました。日本には、落日を歌った歌が実にたくさん残されているんですね。万葉集からありますよ。古今集、新古今集、平家物語、謡曲、浄瑠璃・・・。それから近代になりまして童謡、学校唱歌・・・。それから流行歌、演歌・・・。いたるところに夕陽を歌った歌が満ち満ちている。これはどうしたことだろう。
歌の世界だけではありません。絵の世界でもそうですね。平安時代の大和絵の伝統をずっと追っていきますと、絵描きといわれている人のほとんどが必ず落日の光景を描いています。これも不思議なことですね。現代を代表する例えば東山魁夷さんは、いくつも夕焼けを描いた大作がございますね。今度また芸大の学長に返り咲かれた平山郁夫さんのユーラシア大陸、シルクロードを描いた絵の中にも夕焼け空が次から次へと出てきます。これはもう間違いない。日本人は夕焼け信仰で千年、千五百年生活してきたんだと言えるでしょう。
私は以前仕事でフランスのパリに行きまして、4週間滞在したことがあります。仕事をそっちのけで私は美術館を訪ね歩きました。西洋人は落日の光景をどのような絵にしているだろうかということを調べるためです。ルーブル美術館なんてのは3日間行っても全部回ることができないくらい大きいのですが、落日を描いた絵はほとんどないんですね。わずかにバルビゾン派、田園派という絵描きたちの中に見出せるくらいであります。私は先ほどイスラエルに行った話をいたしましたけれども、イスラエルでも夕刻になると私は目を凝らして落日を観察をしたのですが、これはもうほとんど胸に響いてこなかった。インドの落日も見ました。アメリカの落日も何回か見ました。やはりそれなりに落日の光景はすばらしいのでありますが、どうも日本列島で眺める落日とは違うのです。
日本人は昔から、あの落日のかなたに浄土をイメージしてきたのではないでしょうか。浄土というのは、人間が死んだ後おもむくべき理想的な国土と言われてきました。これは仏教が日本にもたらした考え方であります。西のかなた、太陽が沈むかなたに理想的な往生すべき国土があるという考え方。沖縄に行きますとニライカナイという海上のかなたに存在する理想の国土が信じられておりますけれども、あれもそうかもしれません。海のかなた、山のかなたにその浄土が横たわっているという感覚ですね。そこへ太陽が落ちていくんですよ。落日を見るということは、自分の運命がそこに象徴的に表されているということでもあります。その太陽がまた翌日になると、東から昇るわけであります。それは人生が必ずよみがえる、季節も繰り返しよみがえってくるという再生の考え方とも結びついている。それを象徴するのが落日ですよね。
“夕焼け小焼けで日が暮れて”たったこの1行が、その千年の日本人の心の遺伝子を、実に優しい言葉で表現しているということになるのではないでしょうか。