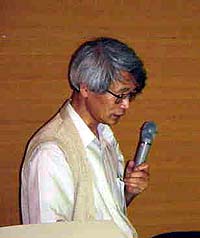大教大附属池田小の痛ましい事件を機に、再び学校は閉ざされるのではないか?との心配が聞かれる。この学校安全の不備をついて起きた事件は、改めて真の意味での開かれた学校づくりとはなにかを問うている。開かれた学校の究極の目的は、一人ひとりの子どもがその持てる能力の全てを生き生きと発揮できるような教育空間を学校という人為的空間から実社会にまで拡大していくことを意味するのではないか。そのことを通じて、また学校は社会や人類の進歩に貢献するという大きな課題の達成を担うことができるというところにある。 残念ながら、いま子どもの現状は極めて憂慮すべき状態にある。これは決して学校にのみ問題があるのではない。家庭、地域の教育力も急速に低下しつつあることを多くの人が感じている。
再び「地域社会と学校との架橋」を この家庭・地域の教育力を高めるためにも「学校を開く」必要がある。 じつはここに掲げるテーマそのものが、教育が生活の中から別れ出て独立の営みとされるようになった近代教育の成立とともに、教育がおわされた課題であるともいえる。それいらい、人々は学校を「開く」ことに懸命に努力をしてきたのである。たとえば、前世紀の半ばにアメリカの教育家オルゼンが、
学校と地域との架橋を真剣に考えて書き著した『学校と地域社会』(School and Community, 1947)は、この課題に取り組もうとする者にとり一つのモニュメントに他ならない。