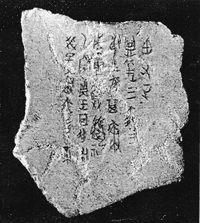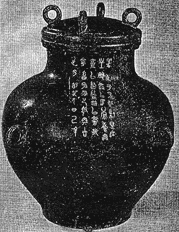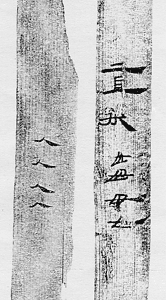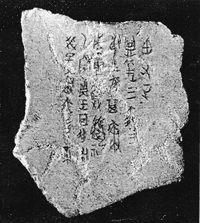 |
| 図1 |
はじめに、文字の役割が、「神」と「人」との意思疎通のためのものから、「人」と「人」との意思疎通のためのものに変わったというお話を簡単にいたします。
漢字は元々、お祭りの道具でした。「神」に物事を祈ったり、あるいは「神」の意思を聞いたりするということが漢字の役割でした。中国では、「神」の意志を受けて皇帝に選ばれるという考え方があるので、歴代の皇帝達は常に、「神」の意思を聞きながら政治を進めるということをします。その時に、「人」である皇帝と「神」である天との間の意思疎通を取ったものが、実は漢字だったわけです。図1は甲骨文の1つです。甲骨文字は、「神」と「人」との意思疎通を図る役割をしていました。亀の甲羅の切れ端に漢字を書いて火にあぶり、どこにひびが入ったかで“○○をしてよいかどうか”を占って、「神」の意思を問うことが甲骨文の役割です。別の面から言えば、“○○したい”ということを「神」に分かってほしいという役割も持っています。
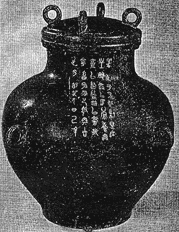 |
| 図2 |
図2は、紀元前6世紀の青銅の壺で、表面に漢字で文章が書かれています。文章の内容は、この壺の持ち主を褒め称えるというもので、この壺の持ち主がこれから後、大変幸せになるように、そしてこの一族が栄えるようにという、「神」に対する祈りの役割を持つわけです。こういう役割の文字というのは、日本にも伝わっています。漢字の字体の歴史で言うと、篆書(てんしょ)と言われるものまでは、基本的に「人」と「神」との意思疎通のための文字です。これが、やがて政治のための道具に変化してきます。例えば、高句麗の「広開土王」という王様の業績を記念して作った石碑があります。これは、「神」に対して王の業績を称えるだけではなく、その国家の人民に対して王の権威を示すという点で、政治的な役割を持っているのです。
紀元前3世紀に秦の王朝が中国を統一して、この時に、隷書という書体が発明されました。この隷書は、篆書(てんしょ)までと違って、「人」と「人」との意志疎通を図るための文字です。隷書の「隷」は奴隷の「隷」と書くように、「奴隷でも書ける」「奴隷が分かる」という意味を持ち、それまでの権威のある文字に対して実用の文字という意味を持っています。これは字の形が大変直線的な、そして抽象的な形に変わりました。その隷書の例をご紹介します。
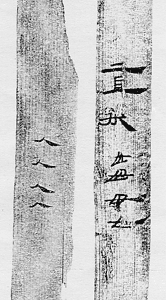 |
| ハネを稽古した木簡 |
右図は、隷書の書き方を習字した木簡です。この隷書は、あまり高度な教育を受けていない人でも字を覚えることができ、速く書くこともできます。そういう意味で画期的な字でした。この隷書を使って、政府の出す命令を地方の隅々まで持っていくと、最初に出された命令がそのまま末端まで伝わります。これが文書行政です。篆書(てんしょ)以前の美しい字体は、誰もが読めるわけではなく、文書をたくさん作って政治の道具に使うというようなことはできません。そこで、紙が発明される以前(大体1世紀まで)は、このように竹や木の切れ端に書いて、命令を伝えるということを行っていました。現在私達も、例えば結婚すれば婚姻届を出し、子どもができれば出生届を出すというように、何事も書類で整理しています。こういう状態を最初に確立したのが、紀元前3世紀の秦の王朝時代でした。そして今で言う、私達が書類を書いたり、手紙を送ったりということにあたる役割を、この木簡に書いた隷書が全て果たしていたわけです。現代に至っても、道具は墨と筆からパソコンに変わっていますが、行っていることの原理は全く同じです。このようにして、文字は人が使うもの、さらには政府が大勢の人たちに命令を伝える道具として変わったのです。