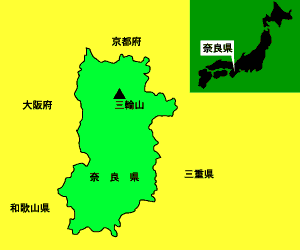 |
古事記の伝えは、大國主神が地上界を治めることが終わりかけた時に、自分ひとりではよく治められそうもないと嘆いた。その時に神が現れた。その神曰く、自分を祀ればここは治まるだろう、と。その神は御諸山(三輪山)の神である。神の時代にこのような神話が伝えられています。地上界を治める上では、三輪の神を祀ることがとても大事だったらしいのです。
ついで、崇神天皇の条が述べていることは、崇神天皇の時に悪い病が流行った。人々が死に絶えそうになった。崇神が困った。夢に神のお告げを聞いて、三輪の山を祀ったところ病がなくなり国がよく治まったという内容です。
これらによって、三輪山の神を祀ることがとても重要な点であったことが知られます。大國主神は天皇とは関わらないが、その神にとっても、地上界を治める上では、やはり三輪山の神がとても大事だったようです。これが6〜7世紀頃の倭の朝廷の貴族たちの感覚だったようです。その中で、額田王は三輪の山への祈りを詠んでいます。
近江に都を遷すことは、朝廷にとって大変大きなことです。国が滅ぶか、生き残るかに関わっていた問題でしょう。このような大事な時になぜ、天皇の祖先の神である天照大神ではなく、三輪の神なのでしょうか?
これについてはいくつか考え方がありえます。一つは天皇の朝廷が大和を去ろうとしているが、天照大神は倭にいるわけではありません。(伝えによれば伊勢の神の宮に祭られたことになっています)倭に関しては、三輪山が故郷の山として歌われたと考えられます。
もう一つは、朝廷の問題、天皇の系譜の問題と関わらせて、天照大神を祭っていた天皇の系譜と三輪の神を祭っていた天皇の系譜とは違うという考え方があります。崇神天皇が三輪の神を祭っていたひとつの王朝で、それに対して天照大神を祭った王朝は、もっと後の新しい別の系統の王朝なのだという考え方がされています。
 愛知県立大学公開講座 |
額田王の三輪山の歌や熟田津の歌、そして天智天皇のこの3つの山を歌った歌は、7世紀中ごろから終わりにかかる頃の、人々の生き方、信仰のあり方を表しており、その背後に東アジアの国々と日本との関わりをひそめています。