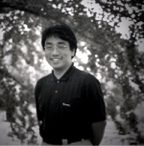 牧野篤先生 |
今、国立大学は独立行政法人化を控え、てんやわんやの状況です。私どもの大学でも現在、例えば、私が講義を担当している大学院教育発達科学研究科は、社会人のためのマスターコースを設けて、昼夜開講しています。平成13年度に初の卒業生を出しました。
この社会人のコースは、私たちが体験できないことをたくさん経験している方々からお話をうかがうことができるので、とても面白いというのが実感です。その方々が上手く社会に出て行くことで、実は大学の地域連携の輪を広げていくことができるのではないかと考えています。その意味では、私ども自身がいい経験をさせていただいています。
さらに、大学と地域社会との連携については、それを必然的に求めるような背景、大きな社会の変化があると考えています。このような変化に対応する形で、大学のもつ機能を組みかえることができないか、という思いがあります。例えば、これから紹介させていただく、シニアプロジェクトにおける大学の研究室と民間企業とが共同で進めるまちづくり、地域起こしの実践が一つの例ですが、このような取り組みにおいて、大学をまちづくりの中心に据えることはできないか、大学が、そこに入って来る人々の循環を作りだしながら、新しい社会を作っていくような原動力、起爆剤にならないだろうかという一つの発想があります。
これは、まちづくりの中心としての大学の機能をいかに地域に開放していくのか、大学に人を呼び込みながら、社会に出していく、そして社会へ出た人々が地域社会で活動されることでその地域を活性化していく、そしてその結果、また大学に還ってくるという形の循環が作れないだろうかということでもあります。
そしてさらに、今18歳人口が年々減少し、大学の冬の時代と呼ばれる状況で、大学の経営を社会人対応にむけて上手く切り換えていくことによって、実は社会貢献ができるような仕組みがあるのではないか、それから、私ども、よく社会から専門バカと言われますが、その専門バカの先生が、情報を提供し、自ら持っている知的なものを提供することによっての社会貢献ができる仕組みが作れるのではないかということです。
厳しい時代です。しかし、このような厳しい時代であるからこそ、大学が中心となって、新しい社会、それはある意味では、生涯学習社会といわれるものでしょう、この社会を構想し、実際に、新たな地域社会、またはそのコミュニティーを作り出す筋道を提示していくことが求められていると思います。そのときの課題は、大きくは次の2つだと思います。
第一は、少子高齢社会の到来という課題です。これから日本は超高齢社会に入っていきます。平成27年(2015年)前後から4人に1人は65歳以上になり、2006年あたりから日本の総人口が減り始めると言われています。また、ある予測では2002〜2003年ぐらいから総人口が減り始めて、今世紀の半ばに1億人をきってしまう。そして今世紀末には、6000万人ぐらいにまで減るのではないかと予測されています。世界の国々において産業社会が出来上がってから、日本が初めて総人口が減少していく社会を経験すると言われています。
その中で私たち自身が直近の20〜30年を考え、どう生きていくのか?が大きな課題になってきます。
第二は、産業構造の転換にともなう雇用の問題です。今、製造業が日本からどんどん中国に移っていて、産業の空洞化が起きています。しかし日本は、国内に新しい産業を作り出すこともしなければ、雇用を作り出すこともしておらず、逆にデフレの進展にともなって、大規模なリストラが行われ、人々の生活不安がひろがっているような状態です。これからの日本は、一握りの勝ち組みとその他多数の普通の人々という二方向に別れていく階層社会になるのではないかという問題があります。
このような社会をどう迎えていくのか、私たちは考えなければならない時代になりました。その中でいかに私たち自身が、働く場を作り出していくかが、大きな課題になっていくのではないかと認識しています。